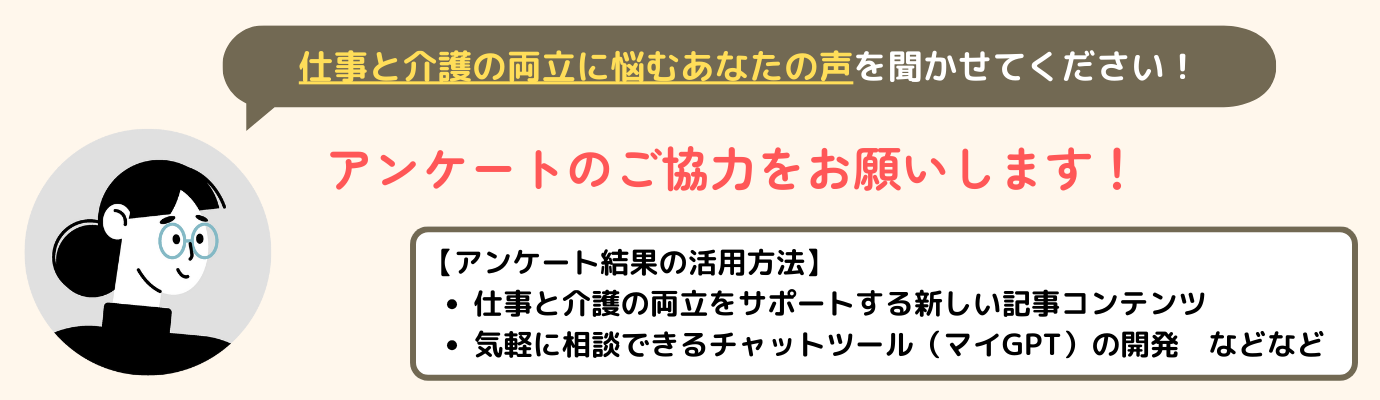訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。
病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護をするにも、自分ではリハビリに対応しきれない」という悩みを、訪問リハビリなら解消してくれます。
この記事では、訪問リハビリとは何なのか、押さえておきたいポイントをわかりやすく解説。訪問リハビリの利用条件や費用、選び方なども詳しく説明します。
目次
訪問リハビリとは?
訪問リハビリとは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの資格を持つ専門家が利用者の自宅を訪問して行うリハビリテーションサービスのことです。
病院や施設に通うことが困難な人や高齢者・障害者などが利用し、主治医の指示をもとに、利用者が自立して生活できるようにサポートします。
訪問リハビリの主な目的は、日常生活の自立支援や機能回復、生活環境の改善です。できる限り自宅で自立した生活を送れるようにサポートします。
対象は利用者だけではなく、ご家族への指導や精神的なサポート、病気予防に関するアドバイスまで、総合的な支援を受けることができます。
利用者やご家族のニーズに合わせたサービスを自宅で受けられるという点が、訪問リハビリの大きな特徴です。
介護保険法での定義
高齢者が適切な介護サービスを受けられるように制定された「介護保険法」において、訪問リハビリの定義は以下のように記されています。
【介護保険法 第8条 第5項】
この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
上記の内容から、訪問リハビリは居宅要介護者のもとに理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリを行うサービスであることがわかります。
居宅要介護者とは、自宅で生活しながら介護サービスを受けている人のこと。原則として、訪問リハビリが利用できるのは、要介護認定を受けている方が原則です。
ただし、医療保険を適用すれば、要介護認定を受けていない方でも訪問リハビリが利用できます。
また訪問リハビリは要支援1または要支援2の方を対象に、要介護状態の発生をできる限り防ぐことを目的とした「介護予防訪問リハビリテーション」としても利用可能です。
介護予防訪問リハビリテーションは、介護がまだそれほど必要でない方向けに対して、身体機能の維持回復を手助けるサービスです。訪問リハビリと同様に利用者の居宅に理学療法士や作業療法士が訪問しサービスを提供します。
【介護保険法 第8条の2 第4項】
この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
なお、訪問リハビリの実施主体は、「病院または診療所」「介護老人保健施設」「介護医療院」の3つに分けられます。
訪問リハビリサービスを提供するには、医師や理学療法士などの人員配置、必要な書類や研修・マニュアルといった運用基準をクリアしなければなりません。
参考として、訪問リハビリのサービス提供で必要な人員・設備を下記にまとめました。
訪問リハビリのサービス提供で必要な人員基準
| 人員 | 基準詳細 |
|---|---|
| 医師 | 専任の常勤医師1以上 (病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院 では、当該病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。) |
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
適当数置かなければならない。 |
訪問リハビリのサービス提供で必要な設備基準
| 基準詳細 | |
|---|---|
| 設備及び備品 | 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。 指定訪問リハビリテーションに必要な設備及び備品等を備えているもの。 |
訪問リハビリのサービス内容
前述したように、訪問リハビリのサービスは多岐にわたります。主に行われるサービス内容は、以下のとおりです。
【訪問リハビリの主なサービス内容】
- 健康状態のチェック(体温測定や服薬確認など)
- 身体機能の回復(歩行訓練・呼吸リハビリなど)
- 日常生活動作の訓練と指導
- 言語訓練やコミュニケーション訓練
- 自主トレーニングの指導
- 福祉用具・住宅改修に関する相談
- 家族や介護者への指導・アドバイス
- 介護・医療保険制度の提案
上記のサービスをただ単に行うだけでなく、定期的に利用者の状態を評価し、リハビリテーション計画の見直しも行います。
訪問リハビリの利用条件
訪問リハビリの利用対象者は、介護保険と医療保険で異なります。
<介護保険の場合>
- 要介護認定を受け、要介護1以上と判定された人
- 要支援1以上と判定された人(※介護予防訪問リハビリの対象)
- 主治医が「介護が必要」とみなした人
- 40〜64歳で特定疾病とみなされ、介護認定されている人
<医療保険の場合>
- 医療保険の被保険者である人
- 主治医が「訪問リハビリが必要」とみなした人
- 退院後や重度の障害者など、訪問リハビリが必要な人
共通の利用条件として、利用者本人および家族の同意が必要になります。
また、理学療法士や作業療法士など専門家が作成する「リハビリテーション実施計画書」も不可欠です。
訪問リハビリにかかる費用
訪問リハビリを利用する際、費用はいくらぐらいかかるのでしょうか。
利用時・月額費用・自己負担額に分けて詳しく説明します。
利用時の費用の内訳
サービス内容や保険の種類によって費用は異なります。
1回20分で利用した場合の費用目安は以下の内訳となります。
<要介護1〜5、1割負担の場合>
- 基本料金:307円
- サービス提供体制強化加算:6円
- 短期集中リハビリテーション実施加算:200円
- リハビリテーションマネジメント加算:180〜483円
- 移行支援加算:17円
1回20分の利用で約710〜1,013円という計算になります。
利用者の条件によって、短期集中リハビリテーション実施加算などの追加料金が発生する仕組みです。
なお、訪問リハビリの利用時間は、1回20分以上の利用は週6回まで(1回40分の利用なら週3回まで)という決まりがあります。
月額費用の内訳
訪問リハビリにおける月額費用の一例を紹介します。下記の表は、40分/週2回のケースです。
| 料金/加算 | 利用料金(自己負担額) |
|---|---|
| 基本料金 | 5,312円 (1回664円×8回) |
| サービス提供体制強化加算 | 96円 (1回12円×8回) |
| 移行支援加算(1回訪問毎) | 144円 (1回18円×8回) |
| リハビリテーションマネジメント加算 (月1回) |
194円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 (1回訪問毎) |
1,728円 (1回216円×8回) |
合計すると、月に7,474円かかります。具体的なリハビリテーションの内容や回数、利用する保険によって異なるため、ケアマネージャーや主治医と相談して決めましょう。
自己負担額
訪問リハビリの自己負担額は、1割負担が原則です。
1回20分の訪問リハビリを利用する場合は、1割負担で1回につき300円前後となります。
ただし、一定以上の所得がある方は、自己負担が2割負担または3割負担になる可能性があるので注意が必要です。
また、サービス内容・提供事業者・利用する時間帯・地域などによって、自己負担額が変わります。
正しい金額を知りたい場合は、担当のケアマネージャーに確認するのがおすすめです。
訪問リハビリのメリットは?
訪問リハビリを利用する主なメリットは、以下の点です。
【訪問リハビリのメリット】
- 自宅でリハビリが受けられる
- より生活しやすい環境が整う
- 精神的な負担が減る
- 1対1で細かい支援が受けられる
- 家族の相談にも対応できる
自宅でリハビリが受けられる
訪問リハビリは専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行ってくれるため、病院や施設へ移動する手間と時間が省けます。
慣れた環境の中でリハビリを受けられるのは、訪問リハビリの大きなメリットと言えるでしょう。
より生活しやすい環境が整う
利用者は自宅でリハビリが受けられるので、日々の生活環境に即した訓練が行えます。
自宅のトイレや浴室などを利用することで、より生活しやすい環境づくりができるほか、リハビリ効果が高まる可能性もあるでしょう。
精神的な負担が減る
自宅でのリハビリは、安心感や心理的なストレスの軽減にもつながります。
住み慣れた自宅なら、病院や施設よりもリラックスしながらリハビリを受けられるでしょう。
また、外出する必要がないため、一緒に暮らしている家族の安心感も増します。
1対1で細かい支援が受けられる
病院や施設でのリハビリでは、他の利用者もいることから、細かいところまでサービスを受けられないことがあります。
一方、訪問リハビリでは1対1でサービスを受けることができるため、細かいところまで支援してもらえるでしょう。
家族の相談にも対応できる
前述したように、訪問リハビリは利用する本人だけでなく、一緒に暮らしている家族のサポートも充実しています。
悩み相談にのってくれたり、利用者が自立するための生活支援でアドバイスをもらったりできるのも、訪問リハビリのメリットです。
訪問リハビリのデメリットは?
訪問リハビリの主なデメリットは、以下の3点です。
【訪問リハビリのデメリット】
- リハビリ内容が制限される
- 他人が自宅に出入りする
- 訪問時間と訪問スケジュールに制約がある
リハビリ内容が制限される
施設を訪れればできるリハビリ内容が、自宅ではできないことがあります。
たとえば、リハビリ機器の利用です。重く大きいリハビリ機器は運搬が難しいため、自宅に持ち運ぶことができません。
病院や施設よりも十分なリハビリを受けられないという点が、訪問リハビリのデメリットです。
他人が自宅に出入りする
訪問リハビリは、理学療法士や作業療法士などの専門家が自宅を出入りすることになります。
人によっては、他人が自宅に出入りすること自体にストレスを抱えてしまうことも。
常に、家をキレイにしておかなければならないというプレッシャーも感じやすくなります。
訪問時間と訪問スケジュールに制約がある
訪問リハビリは訪問時間に制限があるため、サービスの提供範囲が限定され、本人や家族の要望に添えない場合もあります。
また、訪問スケジュールは事業者側の都合によって決定されるので、スケジュールが確保できない可能性もあるでしょう。
他の介護サービスとの違い
類似した介護サービスとして、「訪問看護」「デイケア(通所リハビリテーション)」「ショートステイ」の3つがあります。
それぞれのサービスについて、さらに詳しく見ていきましょう。
訪問看護との違い
訪問看護は、医師の指示に基づき、看護師が高齢者や障害を持つ方の自宅を訪れて医療行為を行います。
医療的なケアを行うかどうかが、訪問リハビリとの大きな違いです。
また、訪問看護の場合は「訪問看護ステーション」から派遣され、訪問リハビリテーションは病院・診療所・介護老人保健施設などから派遣されるといった違いもあります。
| 訪問看護の特徴 | 概要 |
|---|---|
| 利用目的 | 患者の健康状態を維持し、回復を促進すること |
| 利用対象者 | 高齢者や障害、病気を持っている方(全年齢対象) |
| 費用 | (例)1回20分未満で348円(1割負担、要介護1〜5) |
| 要介護度 | 要介護1〜5は訪問看護、要支援認定1〜2は介護予防訪問看護 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 看護師 |

高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
デイケア(通所リハビリテーション)との違い
デイケア(通所リハビリテーション)は、施設または介護医療院に通いながら、理学療法士といった専門スタッフから日常生活動作訓練などを受けるサービスのことです。
利用者は日中の一部またはすべてを施設で過ごすことになりますが、宿泊はしません。
| デイケア(通所リハビリテーション)の特徴 | 概要 |
|---|---|
| 利用目的 | 家族の負担軽減や利用者の社会参加促進、日常生活の向上と改善、心身の健康を支援すること |
| 利用対象者 | 要支援・要介護認定を受けている人 |
| 費用 | (例)1日利用で1,742円(1割負担、要介護1) |
| 要介護度 | 要支援1〜要介護5 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 介護福祉士、ケアマネージャー、社会福祉士など |

デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
ショートステイとの違い
ショートステイは、短期間施設に滞在し、介護や生活支援を受けるサービスのことです。
一般的に、1日から数週間程度の期間、施設に宿泊します。
なお、施設では食事の提供、入浴、排泄の介助、医療的なケア、リハビリなどのサービスが利用可能です。
| ショートステイの特徴 | 概要 |
|---|---|
| 利用目的 | 自宅にこもりがちな利用者の孤立感解消、心身機能の維持回復、家族の介護負担を軽減すること |
| 利用対象者 | 要介護認定を受けている人 |
| 費用 | 1泊2日で3,000〜8,000円ほど |
| 要介護度 | 35歳以上の要支援1・2、要介護1〜5 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 医師、看護師、介護士、生活相談員、機能訓練指導員など |

「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
訪問リハビリを選ぶときのポイント
訪問リハビリの選び方で押さえておきたいポイントは、以下の点です。
【訪問リハビリを選ぶときのポイント】
- 必要な専門スタッフが在籍しているか
- 急変時の連絡や対応がしっかりしているか
- 必要なサービスを提案してくれるか
必要な専門スタッフが在籍しているか
事業所によって在籍している専門職種が異なるため、必要な専門スタッフがそろっている訪問リハビリを選びましょう。
また、専門スタッフのキャリアにも注目してください。
経験のある専門スタッフほど、より効果的なリハビリを受けることができます。
急変時の連絡や対応がしっかりしているか
リハビリ中に急変した場合、すぐに看護師や医師へ連絡が取れるかも大切なポイントです。
急変時、迅速に対応してくれる事業者なら、家族も安心できます。
急変時や緊急時の対応方法は、事前に確認しておきましょう。
必要なサービスを提案してくれるか
利用者の状態に合わせて、必要なサービスを提案してくれるかどうかも大切なポイントです。
たとえば、リハビリの目的を達成した後、今の状態を継続するために、デイケアやデイサービスを提案することがあります。
必要なサービスは何かを一緒に考え、提案してくれる事業所なら安心です。
訪問リハビリを利用するまでの流れ
訪問リハビリを利用する流れは、以下のとおりです。
【訪問リハビリを利用する流れ】
- ケアマネージャーと相談しながら、事業所を選定する
- 必要書類の作成を依頼する
- ケアプランを作成する
- 事業者と契約を結び、サービス利用開始
ケアマネージャーと相談しながら、事業所を選定する
まずは、担当のケアマネージャーに相談し、訪問リハビリの事業所を選定しましょう。
選定した事業所へはケアマネージャーが連絡を取り、利用の可否を確認してくれます。
ケアマネージャーから事業所をおすすめされることもありますが、必ずしも従う必要はありません。
自分でサービス内容などを確認した上で、事業所を選ぶことが重要です。
必要書類の作成を依頼する
事業所の決定後、訪問リハビリを利用したいと主治医へ伝えます。
訪問リハビリを利用するには、「診療情報提供書」や「指示書」などの書類が必要になるため、診察を受けて作成してもらいましょう。
ケアプランを作成する
主治医から訪問リハビリの指示が出たら、ケアマネージャーと事業所の担当がケアプランを作成します。
ケアプランとは、どのような介護サービスを受けるかをまとめたものです。
介護保険制度のもとで提供されるサービスを利用する際は、必要な計画書となります。
事業者と契約を結び、サービス利用開始
ケアプランの作成後、事業者と契約を結べば、サービス利用開始となります。
訪問頻度やリハビリ内容は、ケアプランとリハビリ計画に基づいて行われるのが基本です。
定期的にモニタリングを行い、必要に応じてリハビリ計画を調整します。
ビジネスパーソンのみなさまへ
ここまで訪問リハビリのサービス内容やメリット・デメリット、選び方など紹介してきました。
改めて、訪問リハビリの特徴は下記の通りです。
【訪問リハビリの特徴】
- 理学療法士や作業療法士が、利用者の自宅を訪問して行うリハビリサービス
- 日常生活の自立支援や機能回復、生活環境の改善が主な目的
- 介護する家族への指導や精神的なサポートも提供
- 主な対象者は、介護保険法に基づき、要介護認定を受けた方
病院やリハビリ施設に通うことが困難な高齢者や、身体的・精神的な障害により外出が難しい方は、訪問リハビリを利用したほうが良いでしょう。
訪問リハビリの利用を検討している方は、担当のケアマネージャーや主治医に相談するのもおすすめです。