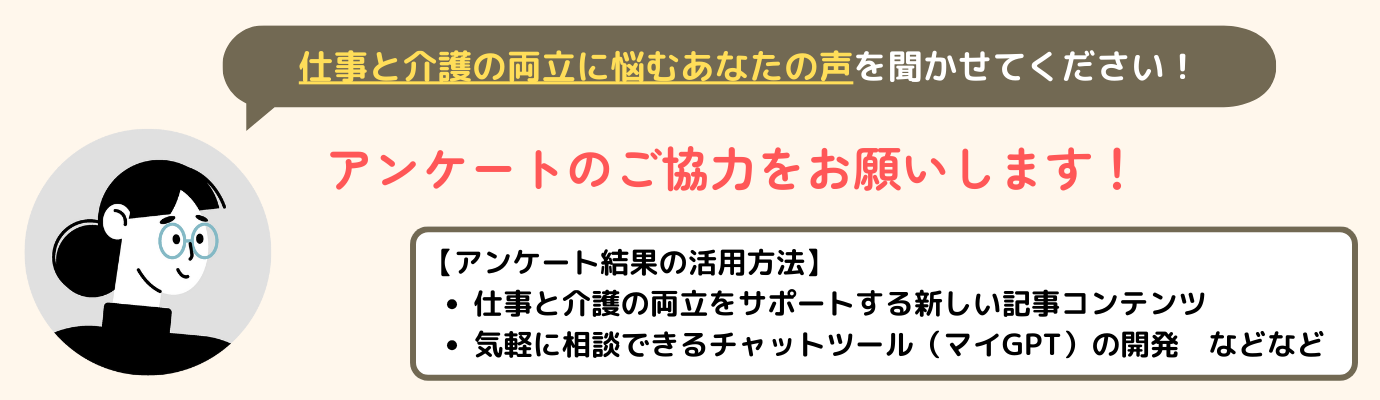離れて暮らす高齢のご家族の、日々の生活を心配されている方は多いのではないでしょうか。
高齢のご両親だけで生活されている場合や、ひとり暮らしをされている場合にも、住み慣れたご自宅でこれまで通りの生活が継続できるようなサポートが受けられたら安心ですよね。
平成24年にスタートした定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、そのようなニーズに応えるサービスと言えます。
この記事では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要をご紹介し、利用を検討する際の参考となるよう情報をお伝えしていきます。
目次
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、訪問介護員または訪問看護師が要介護者の自宅を定期訪問し、介護・看護を提供する24時間対応の介護サービスです。
平成24年4月に施行された改正介護保険法において新設されたサービスであり、通常の定期的な巡回訪問に加えて、随時の通報にも対応します。
訪問介護と訪問看護による連携をはかりながら、高齢者の自立した在宅生活を包括的に支えます。
従来の訪問介護では対応できなかった日に複数回の訪問も可能とし、安否確認や見守り、服薬管理にも利用できます。
高齢者のみの世帯や一人暮らしの高齢者にとって、日々の生活に安心感が与えられるとともに、介護を担うご家族の負担を減らすことが期待できるサービスです。
本サービスは「地域密着型サービス」になりますので、原則としてお住まいの市区町村以外の施設・事業所のサービスは利用できませんのでご注意ください。
介護保険法での定義
介護保険法第8条第15項において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次のように定義されています。
一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者(*1)により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(*2)を行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者(*3)により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。
ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準(*4)に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
*1介護職員初任者研修過程を修了したもの
*2入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談および助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話
*3保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士
*4病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定するものが行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を運営する際の人員の基準は、定期巡回、随時対応訪問を行う訪問介護員、訪問看護を行う看護職員、随時対応サービスに対応するオペレーター、計画作成責任者、管理者となっています。
また、サービスを提供する事業所には、訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業所が訪問看護を行う事業所と連携してサービスを提供する「連携型」事業所があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、サービス名にある通り、「定期的に訪問」する場合や「必要に応じて訪問」する場合があります。
一日に複数回訪問し、一回の訪問は10~20分程度が平均的ですが、要介護度が高くなるにつれて訪問時間や回数が多くなります。
たとえば、一日数回の服薬管理が必要な方や、一人で食事することが難しく介助を必要とする方などに提供されるサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護には以下の4つのサービスがあります。
要介護者の状況に合わせて4つのサービスを組み合わせて利用します。
| サービス | 概要 |
|---|---|
| 定期巡回サービス | 訪問介護員が定期的に訪問し、入浴・食事・排せつ等、日常生活のサポートを行います。 状況に応じて安否確認や健康チェック、見守りのため1日に複数回の訪問もできます。 |
| 随時対応サービス | 利用者である要介護者ご本人やご家族からの連絡に、有資格者であるオペレーターが24時間対応し、 状況に応じたサービスの必要性の判断やサービスの手配を行います。 |
| 随時訪問サービス | 随時対応サービスの連絡を受け、必要に応じて訪問介護を行います。 |
| 訪問看護サービス | 医師の指示に基づいて定期的な訪問を行って、健康状態の確認を行います。 訪問介護と同様に随時訪問にも対応します。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用条件
要介護1から5の認定を受けた方が利用できます。要支援1や要支援2の方はサービスを受けられません。
また、地域密着型サービスとして提供されているため、利用者の住所と同じ市町村内で指定を受けた事業所を利用する必要があります。
それ以外にも、他の訪問介護、訪問看護、夜間対応訪問介護サービスとは、サービス内容が重複するため併用はできません。
| 条件 | 利用可能 | 利用不可能 |
|---|---|---|
| 要介護度 | 要介護1以上 | 要支援では利用できない |
| 住所 | 事業所と同一市町村内 | 事業所と市町村が異なる |
| サービスの利用状況 | 他の訪問サービスを利用していない | 他の訪問サービスを併用 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護にかかる費用
従来の訪問介護や訪問看護では、1回の訪問ごとに利用者負担がかかりましたが、定期巡回・随時対応型は月毎の定額料金となります。
また、利用者負担額は利用者の要介護度や、地域によって異なります。
利用時の費用の内訳
利用時の費用は1ヵ月ごとの月額制で、介護度やサービス内容、事業所ごとに料金が異なります。
また料金の算出方法は地域ごとに定められた地域単価で計算しますので、地域によっても料金は異なります。
また、利用サービスに応じて以下の減額もあります。
- 通所系サービスであるデイサービス等を利用している場合には、1日分の利用料の33%相当額が日割り計算により減額されます。
- 短期入所系サービスであるショートステイを利用した場合には、利用日数に応じた日割り計算が行われます。
月額費用の内訳
月額費用は、以下の計算式によって算出します。
地域単価×単位数=○○円(1円未満切り捨て)
連携型の事業所をで看護を利用する場合は、訪問看護事業所に別途利用料がかかります。
(※厚生労働省 「地域区分について」より)
【(例)要介護2の利用者が東京23区で一体型事業者の介護・看護のサービスを利用した場合】
- 地域単価11.40円(一級地)
- 単位数12,985
- 11.40×12,985=148,029円
| 要介護度 | 一体型 | 一体型 | 連携型 |
|---|---|---|---|
| 介護・看護 | 介護のみ | 介護のみ | |
| 要介護1 | 8,312 | 5,697 | 5,697 |
| 要介護2 | 12,985 | 10,168 | 10,168 |
| 要介護3 | 19,821 | 16,883 | 16,883 |
| 要介護4 | 24,434 | 21,357 | 21,357 |
| 要介護5 | 29,601 | 25,829 | 25,829 |
自己負担額
自己負担額は原則月額費用の1割と決められていますが、一定以上の所得額がある方は2割、もしくは3割負担となります。
上記の月額費用内訳で挙げた例のように月額費用が148,029円の場合には、14,802円が自己負担額となります。(1割負担の場合)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリットは?
ここからは定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスにはどのようなメリットがあるのか、具体的にご紹介していきます。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット】
- 生活リズムに合わせたサービス
- 1日に複数回の定期訪問
- 24時間365日の緊急時対応
- 定額利用料で受けられる
- 幅広く包括的なサービス
生活リズムに合わせたサービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、利用者の状況に応じたサービス計画が柔軟に作成できるため、個々の生活リズムに合わせてサービスが受けられるというメリットがあります。
介護度が高くなりつつあり、オムツ介助や寝返り介助など、訪問介護の頻度を高くしなければ生活の質が維持できなくなっている方にとって適したサービスと言えます。
1日に複数回の定期訪問
状況に応じて、生活支援だけではなく安否確認や服薬確認、見守り、おむつ交換などの目的で短時間の訪問サービスを受けられます。
通常の訪問介護では難しかった1日のうちに複数回の訪問も受けられるため、安定した生活を支えられます。
24時間365日の緊急時対応
定期巡回の他にも、随時対応サービスが受けられることは大きなメリットと言えます。
利用者は専用の機器を使ってすぐにオペレーターに相談ができることから、緊急時の不安が解消されます。
オペレーターは相談内容に応じて、必要なサービスを提供します。
定額利用料で受けられる
従来の訪問介護や訪問看護では、利用するごとに費用が発生していました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、月額の定額料金でサービス利用ができます。
随時対応サービスを何度も利用した場合でも、追加費用がかからないため安心して利用できます。
幅広く包括的なサービス
介護と看護の両方を受けられるというメリットがあります。
見守りや安否確認を含めた日常生活の支援に加えて、退院後の生活に不安がある方や医療的なケアを必要とする方にとっても、随時訪問看護のケアが受けられ、安心した在宅生活が包括的にサポートされます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護のデメリットとは?
メリットが多くある定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスですが、サービスの特徴に伴うデメリットもあります。
ここからはデメリットについて5つご紹介します。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護のデメリット】
- 併用できないサービスがある
- 同一エリア内の事業所でなければ利用できない
- 利用料が割高になる可能性がある
- サービス環境が変化する
併用できないサービスがある
訪問介護や訪問看護、夜間対応型訪問介護など、類似の介護サービスは併用できません。
そのため、他の訪問介護・看護サービスの利用を希望する場合には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を中止しなければいけません。
利用される方の状況に応じた適切なサービス利用を、慎重に検討することが大切です。
同一エリア内の事業所でなければ利用できない
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは、地域密着型サービスとなっています。そのため、事業所指定を行った市町村内でなければ利用できません。
近隣であっても市町村をまたいだ利用はできないため注意が必要です。
利用料が割高になる可能性がある
月の利用料が定額になっているのは、利用頻度が高い方の利用を想定しているサービスだからです。そのため、サービス利用頻度があまり高くない方が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合に、利用料が割高になってしまう可能性があります。従来サービスを組み合わせた場合と比較検討して選ぶようにしましょう。
サービス環境が変化する
すでに訪問介護や訪問看護サービスを利用している方が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用し始める場合に、訪問介護・看護スタッフ、またはサービス提供事業所ごと、これまでと変わってしまう場合があります。
環境が変わることで安定した支援が受けにくくなったり、あらたに関係性を築くことが利用される方の負担になったりする可能性があります。
他の介護サービスとの違い
高齢者の在宅生活を支える介護サービスは、他にもあります。それぞれのサービスにはどのような違いがあるのでしょうか。
サービス内容や費用、利用者の要介護度などを比較してご紹介します。
訪問介護との違い
訪問介護では市町村をまたいで利用できますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は同一市町村内の事業所でなければサービスを受けられません。サービス対応時間も異なります。
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問介護 | |
|---|---|---|
| 対応時間 | 24時間 | 日中のみ |
| 費用 | 定額制 | 利用回数に応じる |
| 利用可能頻度 | 短時間で日に複数回 | 回数に限度がある |
| 要介護度 | 要介護1、2の利用が5割 | 要介護1、2の利用が6割 |
訪問看護との違い
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、訪問介護と訪問看護が一体となって包括的なサービス提供が行われる点が大きく異なります。
それにより、比較的介護度が高く、頻回に訪問によって在宅生活のサポートを必要としている利用者に適したサービスと言えます。
夜間対応型訪問介護との違い
一番大きな違いはサービス提供時間です。また医療ケアができるかどうかも異なります。
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 夜間対応型訪問介護 | |
|---|---|---|
| 対応時間 | 24時間 | 18時〜8時 |
| 医療対応 | 看護師による医療ケアが可 | 不可 |
| 費用 | 定額制 | 利用回数に応じる |
| 要介護度 | 要介護1、2の利用が5割 | 要介護3以上の利用が6割弱 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を選ぶ時のポイント
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴はここまでご紹介してきたとおりです。
では、実際に利用をスタートする際に気をつけるポイントはどのようなものでしょうか。
空き状況
希望するサービス事業所に空きがあるかどうかを確認しましょう。
生活リズムに沿って、どのようなサービスがどのくらいの時間必要になるかを確認します。
訪問してもらう時間やしてもらいたい介助などを具体的にして、サービス提供を行う事業所に対応できるかどうかを相談依頼します。
自宅からの距離
自宅からサービス事業所までの距離に気をつけて選びましょう。
地域密着型のサービスであるため、同一市町村内の事業者でなければ利用できないことも理由の1つではありますが、緊急時の随時対応サービスを利用する際のことを考えて、迅速な訪問対応ができる距離であることが大切です。
併用できないサービスがある
併用できないサービスがあるため、利用を検討する際にはそれぞれのサービスのメリット・デメリットをよく確認して、生活に適したサービスを選ぶことが大切です。
併用できないサービスは以下の3つです。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 夜間対応型訪問介護
同一市町村内の事業所を選ぶ
地域密着型サービスとして提供されている定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居住地の同一市町村内にある事業所を選ぶ必要があります。
距離は近くても市町村をまたいでの利用はできないため、事業所選択の際は注意して選びましょう。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するまでの流れ
それでは実際にサービスを利用する際の手続きは、一体どのようになるのでしょうか。流れに沿って確認していきます。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用するまでの流れ】
- 要介護認定申請
- 要介護認定調査を受ける
- ケアプランを作成する
- サービス事業所を選ぶ
要介護認定申請
居住地の市町村の役所や地域包括支援センターで、要介護認定の申請を行いましょう。
申請は利用するご本人のほか、ご家族や地域包括支援センターや居宅介護支援事業者も代行できます。
要介護認定申請に必要となる書類は以下のとおりです。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証・医療保険被保険者証
- マイナンバーが確認できるもの
- 主治医の情報が確認できるもの(医師意見書が必要となるため)
要介護認定調査を受ける
要介護認定申請を行うと、お住まいの市町村の調査員が自宅に訪問します。
ご本人およびご家族との面接によって日常生活の様子や心身状態に関する調査を行い、その結果と主治医からの病状に関する意見書の内容によって認定結果が出ます。
ケアプランを作成する
認定結果に従って利用するサービスを具体的に決めます。
認定結果は要支援1・2・要介護1・2・3・4・5の7段階となります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する場合には要介護1以上の認定結果が必要となります。
ケアマネージャーに「ケアプラン」という介護サービスの計画書を作成してもらうため、居宅介護支援事業者を選んで契約します。
サービス事業所を選ぶ
ケアプランが作成されたら、実際のサービスを行う事業所を選択します。
ケアマネージャーからの情報や、利用者ご本人やご家族の希望される事業所を選び契約します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスは地域密着型サービスであるため、お住まいの市町村内にある事業所を選ぶようにします。
ビジネスパーソンのみなさまへ(まとめ)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、居宅介護サービスの中では唯一24時間365日のサービス提供が行われるものです。
サービスの特徴は以下のとおりです。
- 生活リズムに合わせて1日に複数回の定期巡回訪問ができる
- 緊急時は随時通報による相談ができる
- 随時通報の相談内容に応じて随時訪問が受けられる
- 訪問看護による医療的ケアが受けられる定期巡回・随時対応・訪問看護を組み合わせ包括的サービスが受けられる
- 定額制で限度額を気にせず利用できる
利用を決める際には類似のサービスである訪問介護や訪問看護、夜間対応型訪問介護などのサービスと比較検討してみましょう。
日常生活の細やかなサポートを受けることでご本人やご家族の毎日が安心したものとなるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを利用してみませんか。