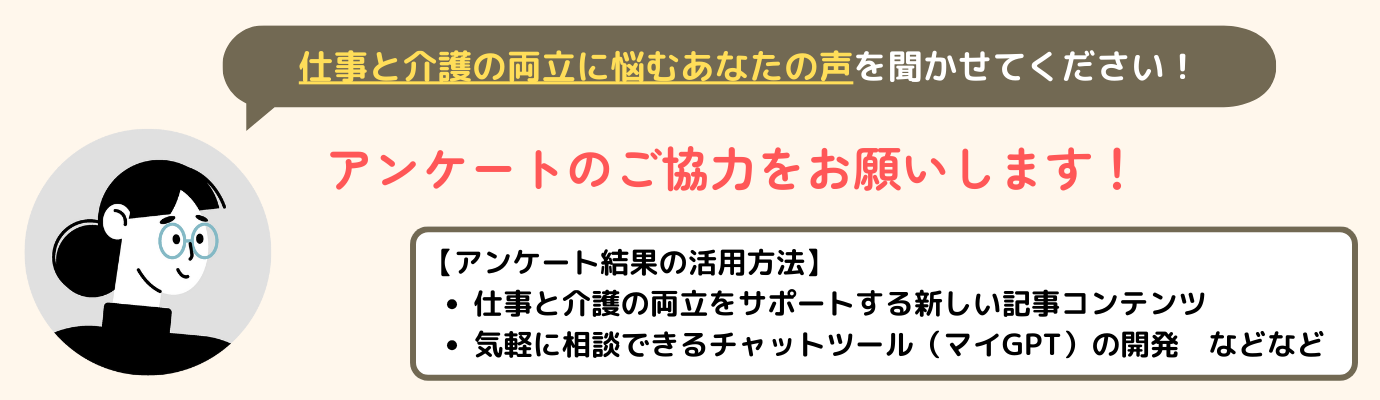現在の日本は超高齢化社会であり、厚生労働省「人口減少の見通しとその影響」によると、今後さらに高齢化率は2030年には32%、2050年には40%になっていくと言われています。
今後さらに超高齢化社会が進んでいくとされていながら、すでに多くの方が「介護疲れ」に悩まされているのが現状です。
特に、団塊ジュニアと呼ばれる40代から50代の世代においては、会社においても重要な職務を担いながら、高齢の親の世話をしなくてはいけないという二重のプレッシャーの中で働いているビジネスケアラーが増えているそうです。
経済産業省の「介護政策」によると、ビジネスケアラーは2020年時点で262万人と推計されており、2025年時点で307万人にまで増えていく見込みとのことです。
ビジネスケアラーなど介護者の方々の介護疲れが溜まってしまうと、要介護者へしっかりとした介護ケアがしきれないだけでなく、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼし、介護者ご本人の精神的、身体的な健康や経済面にも悪影響を及ぼしかねない深刻な課題です。
この記事では、介護における心身の疲れている介護者、ビジネスケアラーの方々の悩みや不安を解決・サポートするために、介護の負担を軽減する方法や役立つ介護サービスをご紹介します。
※参考サイト:厚生労働省「人口減少の見通しとその影響」
※参考サイト:経済産業省「介護政策」
目次
介護への疲れやストレスを感じる人は多いのか?
介護者が感じている介護への疲れやストレスは、多くの家庭で無視できない問題となっています。
前提として超高齢化社会と言われている日本では、厚生労働省が毎年発表している「国民生活基礎調査の概況」の令和4年度の調査によると、日本の全世帯の中で「高齢者世帯」が1693万1千世帯(31.2%)を占め、平成28年の1327万1千世帯(26.6%)から大きく増加しています。
そして、高齢者人口自体も、平成28年には3531万5千人であったのに対し、令和4年には4029万7千人に増加しており、超高齢化社会の進行は明らかな状況です。
その中で、平成28年度の調査では、日常生活で悩みやストレスを感じている主な介護者が68.9%に上っています。
令和4年度のデータには、該当の調査結果が出ておらず明確な数字は掲載できませんが、「介護疲れ」の状況に大きな変化は見られないため、平成28年度と同等のおよそ60~70%の介護者の方々が悩みやストレスを感じていることが想定できます。
今後さらに高齢化率が上昇していくことが見込まれており、今後さらに多くの家庭が介護の現実に直面し、介護負担が広がることで介護疲れに悩む介護者が増えていく非常に可能性が高い状況です。
このように大きな社会課題となっている「介護疲れ」ですので、今現時点で介護の悩みを抱えている方は、ぜひ1人で抱え込み過ぎないように無理をしないでいただければと思います。
介護者が感じる介護疲れの要因は?
ビジネスケアラーなど介護者の方々は、身体的、精神的、経済的な負担を抱えながら日々の介護に向き合っていらっしゃるでしょう。ここでは、介護疲れの3つの主な要因をご紹介します。
自己分析の意味でも、ご自身が感じている介護疲れがどのような要因から来ているのか再認識いただき、悩みを解決する手段を見つけるきっかけにしていただければ幸いです。
介護疲れの要因:身体的要因
日々行う介護は身体的にも大きな負担となっているはずです。例えば、車椅子からベッドへの移動介助、深夜のおむつ交換、食事介助など、重労働を介護者がやらなければいけません。
これらの介助は、介護者の腰や肩にも負担がかかり、疲労や体の痛める要因になりえます。夜中に介護が必要な場合もあり、夜間に何度も起こされることによる睡眠不足となることでカラダが休まらない日々も続くこともあるでしょう。
介護疲れの要因:精神的要因
介護ではカラダへの負担以上に精神的な負担を感じる方も多いかもしれません。
要介護者からの日常的なお願いごとや、認知症からくる繰り返し行動、コミュニケーションが上手く取れないことでのイライラなどが、ストレスの原因となります。
1人で介護負担を負っている場合、支援が得られないことでの孤立感やイライラなど精神的なストレスが溜まる要因となるでしょう。結果的に、介護者が「介護うつ」になることも少なくありません。
介護疲れの要因:経済的要因
介護にかかる費用をどのように捻出するかも悩みの1つでしょう。介護保険でカバーされる部分もありますが、自己負担額も決して少なくなく、自己負担割合も今後上がっていく可能性もあります。
加えて、要介護度が高くなるにつれて介護に必要な費用は増えていきます。そのため、しっかりと面倒を見たいという要介護者への優しさから、介護者が仕事時間を減らしたり、退職してしまうとなると、家計はどんどんと苦しくなり、経済的な圧力が大きくなっていくことになってしまいます。
介護疲れの要因:認知症介護の要因
認知症介護が、介護疲れの原因であることも多くあります。身体的に自立している人であっても、認知症の方は意思疎通が難しく、介護が大変になるのです。
認知症の代表的な症状としては、
- ひとり歩きをする(徘徊する)
- 外出したまま道に迷う
- 夜間に活動する(昼夜逆転)
などがあります。
おむつ交換などの身体的な介護が必要なくても、上記のような症状があれば常時見守りが必要です。このように認知症介護は、家族の大きな負担となっていることが多くあります。
介護疲れによって起きてしまう問題は?
多くの介護者が感じる介護疲れをそのままにしてしまうと、介護者の精神状態や生活全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。精神的、身体的な負担が積み重なることで、起きてしまいかねない問題をご紹介します。
ご紹介する問題が起きないためにも、「介護疲れ」を放置することのリスクを理解しておきましょう。
虐待や事件につながってしまう
介護者にとっては、介護疲れは感情のコントロールを難しくし、心もカラダも休めるはずの家の中で極度のストレス状態が続くことで、思わぬ暴言や暴力につながることがあります。
さらに、介護者自身が感情をうまく処理できないと、ストレスが積み重なり虐待に発展してしまうこともあります。また最悪の場合、介護を巡る悲惨な事件に発展することもあります。
東京都福祉局の調査によると、令和4年の介護者による虐待の相談・通報件数は4,444件と、前年からも6.9%と増えており、高齢者への虐待は現実的にも起きかねない事象と認識すべきかもしれません。
(参考:東京都福祉局「令和4年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」)
介護者自身がつぶれてしまう
長期間の介護は、介護者の心身の健康に悪影響を及ぼすことが多いです。心理的な負担が大きいため、介護うつとなるリスクが高まります。
また、不規則な生活や睡眠不足が体調に影響を与えてしまいます。
株式会社インターネットインフィニティーは要介護高齢者の医薬品独自調査サービス『CMNRメディカル』にてCMNRメディカル(第30回) 「うつに関するアンケート」を実施したところ、利用者や家族から「死にたい」と言われたり、自殺を図られたことがある介護支援専門員(ケアマネジャー)の割合は55.9%にのぼる結果が出たようです。
加えて、アンケートの結果から推定約63万人の介護家族が抑うつ状態にありながらも受診していないと想定されており、いかに介護者の方々が介護をご自身で抱え込んでしまっているかが分かる結果となっています。
(参考:「介護うつ「死にたい」と言われたケアマネ56%も、早期の受診勧奨に難あり~磁気刺激や光療法「知らない」7割(治療認知調査)~」)
このように、介護うつとなってしまう可能性は誰にでもあることを知っておく必要があると言えます。
介護離職による経済的な生活への悪影響
約300万人まで増えていると言われるビジネスケアラーにとっては、介護に追われるあまり、やむを得ず「介護離職」を選択してしまう人もいるようです。
経済産業省が出している「介護政策」の推計では介護離職を選択している方は2025年で約10万人になるとされています。
介護離職を選ぶ方は、介護が落ち着いた際に、再就職を目指すことを想定されていると思いますが、再就職出来た場合の年収を想定しておく必要があるでしょう。
仮に介護期間を1年ほどと想定した場合、1年のブランクがあると離職前の年収を担保することは難しく、下がってしまうことは明らかです。そして、再就職できない可能性も当然考えられます。
2014年と前のデータですが、明治安田総合研究所の「仕事と介護の両立と介護離職に関する調査結果」では、再就職後の年収は男性平均で556.6万円から341.9万円へ4割下がり、女性平均では350.2万円から175.2万円と半減しているようです。
介護離職は、長期での経済面でも大きな悪影響になり、相当なリスクがあることを認識しておく必要があります。
(参考:経済産業省「介護政策」)
(参考:明治安田総合研究所「仕事と介護の両立と介護離職に関する調査結果」)
(参考:酒井 穣 (著)「ビジネスケアラー 働きながら親の介護をする人たち」)
家庭崩壊につながってしまう
介護疲れが原因で、家族関係が悪化し家庭の崩壊につながってしまうこともあります。
例えば、介護の負担が子の嫁など一人に集中してしまい、その結果、夫婦間の関係が悪化してしまうようなケースです。
周囲からの支援がなく、介護を一人で抱えてしまうことで、介護者は孤立化してしまう傾向があります。ストレスが更に大きくなり、家庭内での不協和音となってしまうことがあるのです。
介護疲れが深刻化してしまう前に、できる限り適切な介護支援の体制を整える必要があります。
万全な体制を整えるためにも、介護の支援制度や介護保険サービス・介護保険外のサービスの理解、介護に関しての相談を誰にすれば良いのかなど介護の知識を高めるようにしましょう。
介護に疲れたときの心の持ち方
介護の疲れを少しでも軽減するためにも、心の持ち方を見直してみるのも1つの手です。心の持ち方1つで介護者の負担感が大きく変わることがあります。
介護疲れを感じたときに心がけたいポイントをいくつかご紹介します。
介護疲れを感じたときに心がけたいポイント
- 介護は私がすべきと背負い込まない
- 私が「できる範囲」をやる
- 気軽に相談できる心のよりどころを見つける
介護は私がすべきと背負い込まない
親の介護をする中で、「自分がすべき」という強い責任感から、全ての負担を自分1人で背負い込んでしまうことがあるようです。
しかし、いつまで介護期間が続くかは分からないため、先の見えない状況下では背負い込み続けることは現実的ではありません。
そのため、介護は1人だけで行うものではなく、家族や親戚、介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センターなどに協力してもらうことが大切です。自分一人で解決しようとせず、周囲のサポートを積極的に求めましょう。
私が「できる範囲」をやる
完璧な介護を求めることは、介護者の心の負担を大きくする原因となってしまいます。すべてを完璧にこなそうとするのではなく、「自分自身はできる範囲の介護をする」という心構えが重要です。
無理なく続けられる介護を心がけることで、長期にわたる介護生活を支えることができます。自分自身ではできない部分は介護のプロに相談することが、要介護者への質の高いケアにつながると認識しましょう。
気軽に相談できる心のよりどころを見つける
介護をする中で感じる孤独や不安を、1人で抱え込まないことが重要です。信頼できる家族や親族、ケアマネジャーなど、気軽に相談できる人を探しましょう。それによって、心の負担を軽減することができるでしょう。
介護に悩む人たち同士が集まる家族会などのコミュニティもありますので、そのようなコミュニティに参加し、支え合うことも良いでしょう。
ちなみに、家族会などの情報は、社会福祉協議会や地域包括支援センターなどに掲載されています。
介護に疲れたときの対処方法は?
介護に疲れたとき、具体的にどうすれば良いのか分からない方も多いでしょう。このセクションでは、介護に疲れたときの相談先や支援制度・介護サービスをご紹介します。
介護者ご本人が些細な悩みやストレスだと感じていても、最悪の結末を招かないためにもまずは1人で抱え込まず、介護のプロに相談することをおすすめします。
担当介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談する
担当の介護支援専門員がいる場合は担当介護支援専門員に相談しましょう。介護支援専門員は介護の専門家であり、介護サービスの調整役を担っています。
介護者ご自身の疲労が蓄積しているのであれば、現在のケアプランを見直し、より実情に見合ったケアプランへ調整していく必要があります。
【相談のポイント】
- 利用している介護サービスの再評価
- 利用している介護サービスが被介護者の状況や介護者の負担に適しているかを再評価してもらいましょう。
- 追加・変更すべき介護サービスの提案
- より介護者の負担を軽減できる介護サービスや支援がないか確認してもらいましょう。
- 心理的なサポートの相談
- 介護者自身の心理的な負担を介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談しましょう。必要であれば専門カウンセラーを紹介してもらうことができます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談は、介護サービスを最適化するだけでなく、介護者自身が抱える介護疲れを解消するための重要な一歩となります。
定期的に状況を共有し、必要に応じて柔軟に介護サービスを調整することが、介護疲れを軽減する上で効果的です。
また、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)を変更したい場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が在籍している居宅介護支援事業所へ相談してみるのも良いでしょう。また、直接伝えにくい場合には、管轄の地域包括支援センターへ相談することも可能です。
身近な地域包括支援センターへ相談する
まだ介護認定を受けておらず自宅介護を続けているため担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいないという場合は、お近くの地域包括支援センターに相談しましょう。
地域包括支援センターは区市町村、または区市町村から委託をうけた法人が運営しています。高齢者が安心して生活するために高齢者やそのご家族へのサポートを担っています。保健師や主任介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士の資格を持った方が相談に乗ってくれますので、安心して相談することができるでしょう。
介護サービスに関しての相談や要介護認定の申請支援も行ってくれるため、介護について相談する当てがない場合はお近くの「地域包括支援センター」へ相談すると覚えておきましょう。
下記では、地域包括支援センターが行ってくれるサポートをいくつかご紹介します。
地域包括支援センターのサポート
| サポート内容 | 概要 |
|---|---|
| 総合相談支援 | 高齢者の各種相談に幅広く対応し、
必要なサービスや制度を紹介するなど支援を行います。 |
| 権利擁護 | 高齢者の権利を守り、
成年後見制度の活用などをサポートします。 |
| 介護予防ケア | 要支援認定を受けた高齢者に対して介護予防プランを作成し、
適切なサービスを提供します。 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント | 地域の専門家と連携して高齢者の課題解決や調整を行います。 |
地域包括支援センターについては下記の記事にて詳しくご紹介していますので、そちらもご覧ください。

介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
社会福祉協議会の民生委員や地域福祉委員に相談する
社会福祉協議会は、地域社会において福祉活動を推進し、住民の生活や福祉に関するさまざまなサポートを行う社会福祉法人です。
社会福祉協議会には、厚生労働大臣から委嘱された民生委員や社会福祉協議会から委託された地域福祉委員が所属しており、生活困難や福祉に関する問題を解決するための支援をしてくれます。
また社会福祉協議会には、ボランティア活動などの情報も多く集められています。例えば、介護について同じ悩みを持つ家族が集まり語り合う「家族会」の紹介や案内などがあります。各種ボランティアの紹介を受けることも可能です。
高齢者の介護に関する相談もできますので、お近くの社会福祉協議会に相談してみるのも良いでしょう。
介護に疲れたときに活用できる育児・介護休業法の制度
介護を行うビジネスケアラーが仕事と介護を両立するための法律として、育児・介護休業法があり、法律で定められている制度をご紹介します。
勤務先の会社でどのような制度が導入されているか確認しましょう。介護離職を避けるためにも、それぞれの制度を把握しておくことが大切です。
育児・介護休業法で整備されている制度
では、具体的に活用できる制度をご紹介します。
| 制 度 | 概 要 |
|---|---|
| 介護休業 | 申し出ることにより、
要介護状態にある対象家族1人につき通算 93日まで、 3回を上限として、介護休業を取得することができます。 |
| 介護休暇 | 要介護状態にある対象家族が 1人であれば 年に 5 日まで、
2 人以上であれば 年に10 日まで、1日単位または半日単位で取得できます。 |
| 所定労働時間の短縮等の措置 | 事業主は、 ①短時間勤務制度(短日勤務、隔日勤務なども含む) ②フレックスタイム制度 ③時差出勤制度 ④介護サービスの費用助成 のいずれかの措置について、 介護休業とは別に、要介護状態にある対象家族1人につき利用開始から 3 年間で 2 回以上の利用が可能な措置を講じなければなりません。 |
| 所定外労働の制限 | 1 回の請求につき1月以上1年以内の期間で、
所定外労働の制限を請求することができます。 請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。 |
| 時間外労働の制限 | 1回の請求につき1月以上1年以内の期間で、
1か月に 24 時間、1 年に150 時間を超える時間外労働の制限を請求することができます。 請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。 |
| 深夜業の制限 | 1回の請求につき1月以上6月以内の期間で、
深夜業(午後10時から午前 5 時までの労働)の制限を請求することができます。 請求できる回数に制限はなく、介護終了までの必要なときに利用することが可能です。 |
| 転勤に対する配慮 | 事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合、
その就業場所の変更によって介護が困難になる労働者がいるときは、 その労働者の介護の状況に配慮しなければなりません。 |
| 不利益取扱いの禁止 | 事業主は、介護休業などの制度の申出や取得を理由として
解雇などの不利益取扱いをしてはなりません。 |
| 介護休業等に関するハラスメント防止措置 | 事業主は、介護休業などの制度の申出や利用に関する言動により、
労働者の就業環境が害されることがないよう、 労働者からの相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。 |
| 介護休業給付金 | 雇用保険の被保険者が要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した場合、
一定の要件を満たせば、原則として介護休業開始前賃金の 67%が支給されます。 |
※参考資料:厚生労働省「平成29年度版「仕事と介護 両立のポイント あなたが介護離職しないために」【概要版】」p.21より
ご紹介したこれらの制度は、勤務先の業種や規模にかかわらず、要介護状態の「対象家族」を介護する労働者が対象となります。
また、勤務先にこれらの制度が設置されていなくとも、介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限は、申し出ることで利用できるので、注意しましょう。
ただし、勤務先の労使協定の定めによっては、勤続年数が 1年未満の方など、取得できない場合もありますので、勤務先への確認は必要です。
利用の手続きと注意点
介護休業や介護休暇などの利用には、以下の手順を踏むことが一般的です。
【介護休業や介護休暇などを活用する一般的な利用手順】
- 申請の準備: 介護する家族の要介護状態を証明する書類の準備。
- 事前の通知: 休業または休暇を取得する意向を事業主に書面で通知(通常は休業開始の2週間前)。
- 協議: 事業主との間で具体的な休業期間や条件について話し合い、合意を形成する。
利用手続きを進める上での注意点として、介護休業や介護休暇などの制度を活用する場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに事前に相談しましょう。
申請書類の準備のサポートや、申請にあたっての勤務先への伝え方や段取りなどもサポートしてくれます。
勤務先での関係性を保つためにも、介護の専門家へ相談した上で、制度活用を進めることでスムーズに活用できるでしょう。
レスパイトケアとして介護サービスを活用する
レスパイトケアとは、「日々の介護疲れやストレスを軽減させることを目的」としており、介護者の介護疲れを癒すためのケアです。
介護疲れやストレスを感じている方は、レスパイトケアとなる介護サービスを利用することで、日々の疲れを癒し、介護生活の不満を解消するようにしましょう。
ここでは、レスパイトケアとして活用できる介護サービスを介護保険サービスと介護保険外サービスに分けてご紹介します。
レスパイトケアで活用できる介護保険サービス
では、レスパイトケアで活用できる介護保険サービスをいくつかご紹介します。
ここでは、それぞれの介護サービスを個別でご紹介していますが、介護サービスをカスタマイズして活用することでより介護者の負担を軽減しながら介護の質を高めることができます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談し、これらのレスパイトケアを活用するようにしましょう。
| 介護保険サービス | 検索リンク |
|---|---|
| ショートステイ(短期入所生活介護) | |
| デイサービス(通所介護) | |
| 訪問介護 | |
| 訪問入浴介護 |
ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイは、一時的に要介護者が介護施設に滞在し、介護スタッフから介護を受けることができる介護サービスです。(連続利用は最長で30日間)
一時的に介護施設に滞在できるサービスなので、介護者が休息を取りたい時や病気や他の用事で一時的に介護が困難な時に利用できます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 一時的に要介護者が介護施設に滞在し、
介護スタッフから介護を受けることができる介護サービス |
| メリット | 24時間体制でのプロのケアが受けられるため、
介護者は日々の介護負担から解放され、リフレッシュする時間を確保できる。 |
デイサービス(通所介護)
デイサービスは、日中のみ介護施設に通うことで、様々なケアやリハビリテーションを受けたり、社交活動を楽しむことができる介護サービスです。
介護者は日中の間、自分の時間を持つことができ、普段の日常の生活や仕事への時間に充てることができます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 |
|
| メリット | 日中には介護施設で介護してくれるため、
日中を仕事の時間に充てることができ、仕事と介護の両立が図りやすくなる。 また、プロの介護スタッフが様々なケアをしてくれるため、介護者は精神的にも安心できる。 |
訪問介護
訪問介護では、ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、食事、排泄などの身体介護や家事支援を行ってくれます。
そのため、介護者は外出する時間や自分だけの時間を確保でき、ストレスの軽減につながるでしょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 |
|
| メリット | 介護者の生活スタイルに合わせて、
介護のプロにお願いしたい介助を決まった時間に対応してくれるため、 仕事と介護の両立が計画しやすい。 |
訪問入浴介護
訪問入浴介護は、専門の介護スタッフが訪問用の浴槽を持参し、家庭での入浴を支援します。
これにより、身体的な負担が大きい入浴介助をプロに任せることができ、介護者の負担が大幅に軽減されます。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 専門の介護スタッフが訪問用の浴槽を持参し、家庭での入浴介護を支援してくれる。 |
| メリット | 体力的にもしんどい入浴介助を介護のプロにお願いできるため、
身体的負担や自己リスクを軽減でき、介護者も安心できるサービス。 デイサービスなどに行けない重度な方も利用できる。 |
これらのサービスを上手く利用することで、介護疲れを感じている方々は大きな支えを得ることができます。
地域の介護支援センターや介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携して、適切なサービスを計画的に利用することが、介護の負担軽減につながるでしょう。
レスパイトケアで活用できる介護保険外サービス
介護保険サービス以外にもレスパイトに活用できるサービスがあります。介護者の生活スタイルに合わせて、賢く使い分けることで、仕事と介護の両立を目指しましょう。
介護保険外サービスなので、保険適用が無い分、介護保険サービスと比較すると費用が掛かることは念頭に置いておきましょう。
自治体によって、補助制度が設けられているサービスもあります。介護保険外サービスの利用にあたっても、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターでの相談をするようにしましょう。
【レスパイトケアで活用できる介護保険外サービスの一例】
- 家事支援・代行:調理、洗濯、掃除、買い物など
- 見守りサービス:安否確認も含めて依頼できる
- 食事宅配(宅食・配食)サービス
- 外出支援サービス:旅行の付き添いなど
- 訪問理美容
- 病院へのレスパイト入院(一か月程度)
介護疲れが耐えられない時は、介護施設への入居も検討しよう
40~50代のビジネスケアラーの皆さんにとっては、特に仕事と介護の両立は非常に難しい問題です。しかし、確実に言えることは、介護離職は避ける必要があるということです。
そのため、地域包括支援センターや介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談し、介護休業などの制度やレスパイトケアのための介護サービスなどをフル活用し、少しでもご自身の負担を軽くしつつ、介護ケアの質を高める体制を整えましょう。
それでも、介護疲れの解消が難しい場合は、介護施設への入居を検討するのも良いでしょう。以下に代表的な施設の入居条件と特徴を簡単に紹介いたします。
| 施設の種類 | 入居条件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | 要介護3以上 | 費用は抑えられるものの、入居待機者が多い。 |
| 介護老人保健施設 | 要介護1以上 | 在宅復帰を目指す高齢者が入居するリハビリを中心とした施設。
施設には医師や看護師、リハビリスタッフが常駐している。 |
| 介護付き有料老人ホーム | 要支援1以上 | 手厚い介護サービスが提供される。
費用はやや高めだが、入居待ちが少ない傾向。 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 自立~ | バリアフリー仕様の賃貸住宅で、
見守りや生活支援サービスが提供される。 |
| グループホーム | 要支援2以上 | 認知症を持つ高齢者がアットホームな雰囲気の中で共同生活できる。
認知症ケアが充実。 |
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 自立~ | 自立度の高い高齢者が利用。
食事や生活支援が提供され、比較的低コストで入居できる。 |
介護施設に入居することで、介護者にかかる介護負担を軽くすることができ、介護者ご自身が自分らしい生活を送ることができるでしょう。ストレスを感じながら要介護者と接するよりも良い関係性を保つことにもつながるかもしれません。
いずれにしても、親の介護を1人で抱え込まず、周りを上手く巻き込みながら介護に向き合うことで、ご自身の介護負担を軽くしていきましょう。