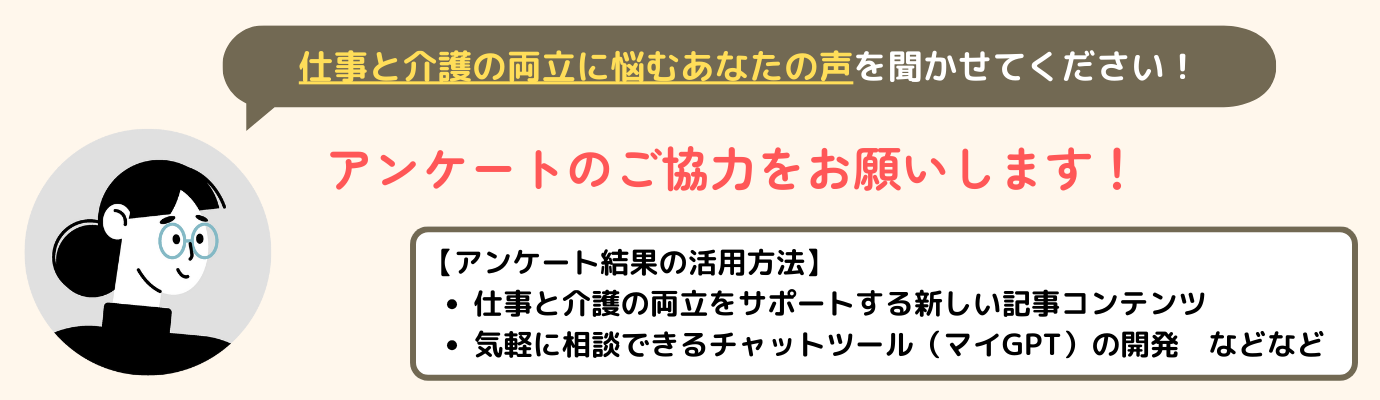介護老人保健施設(いわゆる老健)とは、要介護1以上の高齢者が自宅復帰を目指すための介護保健施設で、おもに「医療ケア」「リハビリテーション」「介護サービス」「認知症ケア」などを行います。
医療ケアでは、医師や看護師が常駐し、健康状態の管理をしてもらえ、かつ病状の変化が有った場合でも迅速に対応出来る医療的な体制が整っています。
また、理学療法士や作業療法士などの専門のセラピストが常駐しており、利用者が在宅生活に戻れるようにリハビリテーションに力を入れています。
この記事では介護老人保健施設のサービス内容や費用、利用するメリット・デメリットを解説します。
目次
介護老人保健施設とは?
介護老人保険施設(いわゆる老健)とは、要介護1以上の方が入所出来る施設です。
自宅での生活が一次的に困難になった方が、リハビリや医療ケアを受けながら在宅復帰を目指すことを目的としています。
入所期間は3か月~半年と定められていますが、これは老健がリハビリによる自宅復帰、終身利用が可能な施設入居待ちのための一次的な利用、といった中間的な役割の施設であることを意味しています。
ここではサービスの内容や、費用、入居条件などをまとめています。
ビジネスパーソンのみなさま方の親やご親族等が施設をお探しの際には、ぜひ老健のサービスも参考にしてみてください。
介護保険法での定義
介護老人保健施設(老健)は、介護保険法では以下のように定義されています。
【介護保険法第8条第28項】
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練 その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
つまり、介護老人保健施設は看護と医療のケアを提供しながら、心身機能の維持と回復のためにリハビリテーションを行い、在宅復帰につなげる施設です。
人員の運営基準は以下の通りで、さまざまなスタッフが連携し、入居者の生活支援や健康管理、機能訓練に取り組んでいます。
| スタッフ | 人員の運営基準 |
|---|---|
| 医師 | 常勤1人以上、100人対1人以上 |
| 薬剤師 | 実績に応じた適当数(300人対1人を標準とする) |
| 看護・介護職員 | 3人対1人以上、うち看護は2/7程度 |
| 支援相談員 | 1人以上、100人対1人以上 |
| 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 | 100人対1人以上 |
| 栄養士 | 入所定員100人以上の場合、1人以上 |
| 介護支援専門員 | 1人以上(100人対1人を標準とする) |
| 調理員、事務員その他の従業者 | 実績に応じた適当数 |
上の表は、すこし分かりづらい表記かもしれませんが、例えば医師の場合、入居者100人に対して、常に1名の医師が施設で待機しているという意味になります。
続いて、設備の運営基準は以下の通りです。
| 設備 | 設備の運営基準 |
|---|---|
| 療養室 | 1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8㎡以上 |
| 機能訓練室 | 1㎡×入所定員数以上 |
| 食堂 | 2㎡×入所定員数以上 |
| 廊下幅 | 1.8m以上 (中廊下は2.7m以上) |
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの など |
また、ユニット型介護老人保健施設の場合、上記基準に加えて下記の基準が設けられています。
※ユニット型介護老人保健市悦とは、居室が共用スペースであるリビングを囲む形で部屋が配置されています。入居者が相互に社会的関係を築き、自立した日常生活を営むことを支援する病院と家庭の中間施設になります。
- 共同生活室の設置
- 療養室を共同生活室に近接して一体的に設置する
- 1つのユニットの定員はおおむね10人以下
- 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、 夜間および深夜は2ユニットごとに1人以上の 介護職員または看護職員を配置
- ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置
介護老人保健施設のサービス内容
介護老人保健施設にはリハビリテーションや看護と医療のケア、介護のサービス、栄養管理があります。
生活を支えるためのあらゆるサービスが受けられますので、安心して利用できます。
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| リハビリテーション | 日常生活の基本的な動作が行えるように訓練 |
| 看護・医療的ケア | 常勤医師や看護師による医療的ケア インシュリン注射や経管栄養、たんの吸引など |
| 介護と生活支援サービス | 食事・入浴・排せつの介護を中心に、着替えや居室の掃除、洗濯、買い物などを支援 |
| 栄養管理 | 栄養やカロリーを栄養士が計算した食事を提供 利用者の持病や嚥下能力などにも個別に対応 |
介護老人保健施設の入居条件
介護老人保健施設への入居には条件があります。
【介護老人保健施設への入居条件】
- 原則65歳以上で、要介護1以上の介護認定を受けている。
- 40歳以上64歳以下の場合でも、特定疾病により要介護認定を受けている。例えば、特定疾病には若年性認知症も含まれており、認知症の方も入所が可能
施設によっては以下のような条件がある場合もあります。
- 伝染病などの疾患がなく、病気での長期入院などを必要としない
また施設独自の入居条件があることもありますので、入所を希望する場合は、あらかじめ施設に入所条件を確認しましょう。
介護老人保健施設にかかる費用
介護老人保健施設を利用するにあたって費用の事前確認は重要です。
ここでは入居時の費用の内訳や月額費用の内訳、自己負担額を説明します。
入居時の費用の内訳
民間企業が運営する有料老人ホームに入居する際には、入居時にまとまった入居費用を求められる場合があります。
しかし、介護老人保健施設は公的な介護保険施設であるため、入居一時金などの初期費用は不要です。
入居にあたって必要な生活用品一式などを用意する費用はかかりますが、民間の施設に比べて初期費用はだいぶ抑えられます。
月額費用の内訳
月額費用としてかかるのは、介護サービス費・居住費・食費・その他費用(水道光熱費・洗濯代・娯楽費など)で、施設によりさまざまですがおおよそ6~17万円です。
介護のサービス内容や施設の種類、居室のタイプなどによって料金が異なり、サービス内容が手厚いほど高額になるケースがあります。
各費用の内容は以下です。
| 月額費用の内訳 | 詳細 |
|---|---|
| 介護サービス費 | 日常生活の自立・機能回復・維持支援のために提供するサービスにかかる費用 |
| 居住費 | 居住費は施設や居室のタイプによって異なり、聞き慣れない言葉だと思われますが、 多床室、従来型個室、ユニット型個室の順に料金が高くなります。 ここでは部屋のタイプでも値段が違う点を理解するようにしてください。さらに、ご夫婦で入居できる2人部屋や個室の場合は特別室料が加算される場合があります。 居住費については介護保険給付の対象外となり、原則として利用者が支払います。 |
| 食費 | 施設で提供される食事の料金ですが、 食費についても居住費同様、介護保険給付の対象外となり原則として利用者が支払います。 |
月額費用は、上記のとおり人によって大きく金額が変ってきます。
施設の状況などでも費用が変わりますので、詳細は事前に各施設に確認し、利用後にトラブルがないようにしましょう。
自己負担額
介護老人保健施設への入居には、費用の1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)の介護保険負担がかかります。
また、介護老人保健施設には、高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費といった費用を軽減できる制度もあります。
| 制度名 | 制度内容 |
|---|---|
| 高額介護サービス費 | 1か月に支払った自己負担が上限を超えた場合、超過分の費用が返還される制度 |
| 特定入所者介護サービス費 | 所得や資産が一定以下の場合、食費と居住費(滞在費)の負担限度額を超える分が支給される制度 |
このような制度も、概要だけの理解で良いので事前に知っておくと良いでしょう。
介護老人保健施設のメリット
介護老人保健施設のメリットについて説明します。
まずはしっかりとメリットを把握して、上手に介護サービスを利用しましょう。
【介護老人保健施設のメリット】
- 在宅復帰を目指せる
- 機能訓練が充実している
- 手厚い医療体制
- 民間施設よりリーズナブル
- 要介護1から利用できる
メリット①「在宅復帰を目指せる」
さまざまな専門家が連携して家庭環境や状況に合わせた個別プログラムを作成し、在宅復帰をサポートします。
福祉用具や住宅改修など、在宅復帰後までを考えたアドバイスも受けられます。
メリット②「機能訓練が充実している」
リハビリを専門とする理学療法士や作業療法士などが常駐しており、個別のプログラムに基づいた機能訓練が受けられます。
施設での生活自体も機能訓練につながる工夫があり充実しています。
メリット③「手厚い医療体制」
常勤の医師がいるほか、看護師も24時間常駐する施設が多く、医学的管理のもとで安心して生活を送れます。
たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアや薬の処方も対応してもらえます。
メリット④「民間施設よりリーズナブル」
前述の通り、公的な施設のため入居時の費用はかかりません。
民間の有料老人ホームと比較すると初期費用が掛からない分リーズナブルに利用できます。
メリット⑤「要介護1から利用できる」
特別養護老人ホームは要介護3以上の高齢者が原則対象ですので、入居には一定の条件が必要になります。
特別養護老人ホームと比べますと、介護老人保健施設は要介護1以上の高齢者が対象になっています。
介護老人保健施設のデメリットは?
介護老人保健施設にはデメリットもありますので、事前にメリットとデメリットの各々をしっかりとおぼえておきましょう。
【介護老人保健施設のデメリット】
- 入居期間が限定的
- 生活支援が不十分
- プライバシーが確保されにくい
- レクリエーションやイベントが不十分
- 内服薬が制限される
デメリット①「入居期間が限定的」
在宅復帰を目的としているため入居期間は原則3か月~半年と限定され、身体機能の改善や回復が見られた場合は退去となります。
看取りに対応している施設もありますが数は少ないのが現状です。終身利用は難しいと考えた方がいいでしょう。
デメリット②「生活支援が不十分」
食事や入浴、排せつの介助などの身体介護サービスは充実していますが、買い物代行や洗濯などの生活支援サービスは十分に提供されない場合があります。
サポートしてくれる家族などが近くにいない場合は、実費で外部業者に委託する必要がでてくることもありますので注意が必要です。
デメリット③「プライバシーが確保されにくい」
4人部屋といった多床室の場合、プライバシーが確保されにくいというデメリットがあります。
個室や2人部屋などが用意されている場合もありますが、特別室料が加算される点は理解しておきましょう。
デメリット④「レクリエーションやイベントが不十分」
レクリエーションはありますが、あくまでも機能訓練に特化したものです。
有料老人ホームのような楽しむためのものや入居者同士の交流を目的としたイベントなどはあまり充実していません。
デメリット⑤「内服薬が制限される」
施設内で薬を処方しますが、薬の費用は介護報酬でまかなうことにあるため、施設側はなるべく安価な薬を勧めたいという考えがあります。
また、今まで服用していた薬であっても施設に勤務している医師の判断で薬が変更になる可能性もあります。
服用している薬がある方は、入所前に施設に確認しましょう。
他の介護施設サービスとの違い
他の介護施設サービスとの違いがわかりにくいとお感じの方もいらっしゃると思います。
それぞれの特徴をまずは簡単にまとめていますので比べてみましょう。
| 施設 | 施設の特徴 |
|---|---|
| 介護老人保健施設 | 在宅復帰と在宅療養支援を行うためにリハビリテーションを提供 |
| 介護付き有料老人ホーム | 食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などの介護・看護ケアが充実 |
| 特別養護老人ホーム | 介護を必要とする方の「終の棲家」となる生活の場と24時間の介護サービスの提供 |
| 介護医療院 | より高度な医療的ケアを必要とする要介護者の長期療養と生活支援を目的とする |
| 施設 | 運営 | 入居金 | 自立 | 要支援 1~2 |
要介護 1~2 |
要介護 3~5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 公的施設 | 無 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
| 介護付き有料老人ホーム | 民間施設 | 有 | △ | △ | 〇 | ◎ |
| 特別養護老人ホーム | 公的施設 | 無 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
| 介護医療院 | 公的施設 | 無 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 |
介護付き有料老人ホームとの違い
次にそれぞれの施設と介護老人保健施設の違いについて詳しく説明します。
まず、介護付き有料老人ホームの場合は、食事や入浴、排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などの介護および看護のケアを受けることが利用目的です。
入居対象者は、自立から要介護の方まで幅広く、介護老人保健施設よりも多くの方を受け入れています。
介護老人保健施設とは異なり、医師や薬剤師はいないので医療行為はできません。また支援相談員ではなく生活相談員がいます。
レクリエーションやイベントが多いのも介護老人保健施設との違いです。

介護付き有料老人ホームは定額で介護サービスが受けられます。レクリエーションやサークル活動など施設ごとの特色あふれるサービスも魅力です。充実した介護サービスと自分らしい生活が両方得られるサービスとして多くの方に選ばれています。 この記事では、介護付き有料老人ホームとはどんな介護サービスを提供して...
介護付き有料老人ホームは定額で介護サービスが受けられます。レクリエーションやサークル活動など施設ごとの特色あふれるサービスも魅力です。充実した介護サービスと自分らしい生活が両方得られるサービスとして多くの方に選ばれています。 この記事では、介護付き有料老人ホームとはどんな介護サービスを提供して...
特別養護老人ホームとの違い
特別養護老人ホームとの大きな違いは入居期間です。
介護老人保健施設は基本的に3か月限定ですが、特別養護老人ホームは「終の棲家」としての利用目的があるため、長期にわたり入居できます。
入居対象者は例外もありますが、原則的には65才以上で要介護3以上の方のため、介護老人保健施設よりもハードルが高くなっています。
費用は介護老人保健施設のほうが介護内容が加算されやすいため、やや高くなりがち。
また、介護が主な目的である特別養護老人ホームにはリハビリテーションの専門スタッフが必ずいるというわけではないです。
さらに、特別養護老人ホームのほうがレクリエーションやイベントが盛んという違いもあります。

特別養護老人ホーム(いわゆる特養)は、要介護3~5の要介護者が入居でき、一般的には民間の介護施設よりも入居費用を抑えられるのが特徴です。 この記事では特別養護老人ホームがどんな介護施設なのか、サービス内容や入居費用、そして入居までの流れなどを細かくご紹介します。 高齢化を背景とした法令を...
特別養護老人ホーム(いわゆる特養)は、要介護3~5の要介護者が入居でき、一般的には民間の介護施設よりも入居費用を抑えられるのが特徴です。 この記事では特別養護老人ホームがどんな介護施設なのか、サービス内容や入居費用、そして入居までの流れなどを細かくご紹介します。 高齢化を背景とした法令を...
介護医療院との違い
介護医療院もまた終の棲家として長期入居しながら療養生活を送れるという点で、介護老人保健施設とは入居期間において大きな違いがあります。
介護医療院は、入居対象は基本的に要介護認定1〜5を受けた65歳以上の方で、要支援は対象外となり、介護老人保険施設とほぼ同じです。
費用も公的施設のため、介護老人保健施設と同じくらいで、民間施設よりも割安です。
スタッフも介護老人保健施設とあまり変わりはありませんが、介護医療院は医療が手厚いため、診療放射線技師がいます。
また、介護医療院は多床室でもプライバシーに配慮した工夫がありますが、介護老人保健施設は多床室の場合、配慮が不十分な場合があります。
介護老人保健施設を選ぶときのポイント
介護老人保健施設を利用しようと決めたら、次はどの介護老人保健施設にするべきかを選ぶことになります。
ここでは選ぶときのポイントを説明します。
【介護老人保健施設を選ぶポイント】
- 建物・設備
- 立地
- 雰囲気
- 在宅復帰率
- 看取りの方針や状況
ポイント①「建物・設備」
実際に見学し、居室や入浴施設、機能訓練室、共用スペースの広さや清潔感、安全対策、機能性などを確認しましょう。
また、清掃や設備のメンテナンス状況、非常時の安全対策などもチェックすることをおすすめします。
ポイント②「立地」
面会で通ったり、何かあったときに駆け付けたりする場合があるため、できればご家族のお住まいからあまり離れていない場所にあるほうがいいでしょう。
ポイント③「雰囲気」
よいサービスが提供されている施設では、利用者の表情も自然と明るくなります。
また、働くスタッフの対応もチェックし、利用者と丁寧なコミュニケーションをとっているか確認しましょう。
ポイント④「在宅復帰率」
在宅復帰率は、介護老人保健施設を退去して、在宅での生活に復帰できた割合を示しています。
リハビリに力を入れている施設は在宅復帰率が高くなる傾向があり、在宅復帰率はリハビリの状況や精度を判断する目安となります。
ポイント⑤「看取りの方針や状況」
在宅復帰を目指す介護老人保健施設は、看取りを前提としていません。
しかし、現実的には必要になるケースもありますので、それぞれの施設の看取りの方針や状況について確認しておくといいでしょう。
介護老人保健施設への入居から退去までの流れ
介護老人保健施設を利用する際の入居から退去までの流れは図のようになります。
次に、それぞれの流れについて解説します。
【STEP.1】要介護認定を受ける
介護老人保健施設に入居するには、要介護1以上の介護認定が必要です。認定は、市区町村にある地域包括支援センター、または役所の高齢者支援窓口で受けられます。
【STEP.2】入居の申し込み
施設に直接入居の申し込みを行います。
しかし、施設の中でも居室のタイプが違ったり、設備が違ったりして、わかりにくい場合があります。
入院中の場合は医療ソーシャルワーカーに、在宅介護を受けている場合はケアマネージャーに相談や確認をしながらすすめましょう。
【STEP.3】「面談」
施設側と入居する本人および家族と面談し、要介護度や現在の心身の状態、生活の状況、必要な医療ケアなどを確認します。
入居後にギャップやトラブルがないように、しっかりと施設側に伝えましょう。
【STEP.4】書類提出、入所判定結果待ち
施設利用申込書や診察情報提供書または健康診断書、看護サマリー(病院や他の施設からの転院などの場合)などの書類を提出します。
施設側が面談や書類をもとに入居判定を行いますので、結果を待ちます。
【STEP.5】契約し、入居
入居が決まったら、契約を締結します。施設の規約や契約書はしっかり確認して、不明点があれば事前に質問しましょう。
また、入居日までに、施設から案内された生活用品などの持ち物も準備しておきます。
【STEP.6】サービスの提供を受ける
医学的管理のもとでリハビリテーションや看護、介護などのさまざまなサービスの提供を受け、自宅復帰を目指します。
日常生活の基本的な動作が行えるように、専門家によって個別にメニューが組まれます。
【STEP.7】審査を受け、延長か退去
基本的な入居期間である3か月ごとを目安に、リハビリテーションでの改善や回復が見られたか、利用の延長が必要かを判断する審査があります。
審査の結果、在宅復帰が可能と判断されると退去、継続が必要と判断されれば延長となります。
ビジネスパーソンのみなさまへ
介護老人保健施設は機能訓練や介護、医療の専門家が連携して、自宅復帰をサポートしてくれる施設です。
しかし、詳細やほかの介護施設との違いなどがわからないという方も多くいらっしゃいます。
そうした方に向けて、介護老人保健施設に関する以下の内容について説明してまいりました。
- 目的は高齢者の在宅復帰支援
- リハビリテーションや医療、看護のサービスを受けられる
- 費用の内訳
- メリットとデメリット
- 介護付き有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護医療院との違い
- 選ぶときのポイント
- 入居から退去までの流れ
介護老人保健施設は基本的に3か月~半年の入居期間となり、長期的な利用はできません。
しかし、自宅での療養はまだ難しいという方とご家族にとって強い見方となってくれるはずですので、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。