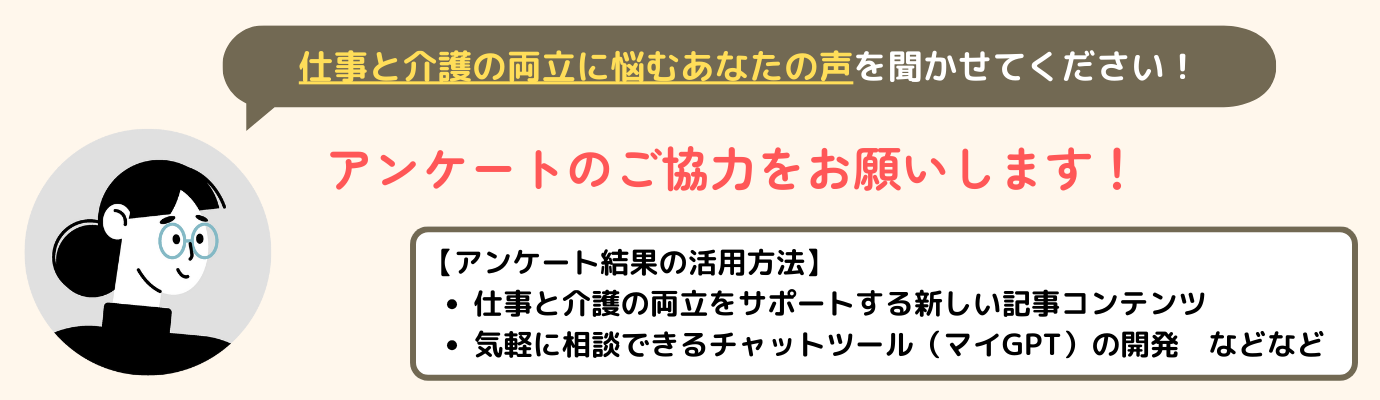高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。
いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。
介護のための介護離職についても考えなければならないビジネスパーソンにとって大きな助けとなるのが医療・介護サービスです。
今回はそんなサービスの中でも、とくに在宅でのケアを行う訪問看護について取り上げます。
訪問看護とは
訪問看護は、病気や障がいを持つ人が自宅で暮らせるように支援するサービスです。
看護師などの医療関係者が自宅に訪問して、主治医の指示に基づき、療養上必要な世話や医療行為を行います。
訪問看護の目的は、自立への援助を促し、その方らしい療養生活を支援することです。
サービス提供は、病院や診療所、または訪問介護ステーションが行うことができます。
また、保険制度としては、医療保険と介護保険のいずれかが適用されます。
どちらが適用されるかは、利用者の年齢や疾患、状態によって変わりますが、介護保険の給付が医療保険の給付に優先されます。
つまり、基本的には介護サービスとして考えられています。
要介護者等については、重病などの理由により主治医の指示があった場合に限り、医療保険の給付による訪問看護が行われます。
介護保険法での定義
訪問看護の介護保険法上の根拠としては、下記の条文が挙げられます。
【介護保険法 第一章第一条】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法 第一章第二条】
第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない
【介護保険法 第一章第八条】
この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
上記の法律を根拠として訪問看護サービスは、利用者の方のご自宅にてその病気や障害に応じた看護を行います。
訪問看護の人員基準とは
訪問看護サービスを提供する事業所側の運営基準としては、人員と設備の基準があります。
人員としては、指定訪問看護ステーションでは保健師や看護師等の看護職員が常勤換算で2.5以上となり、かつ1名は常勤である必要があります。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を実情に応じた適当数配置していることも条件になります。
また、設備基準としては、事業を運営していく上で必要な広さを満たす事務室や設備・備品等が揃っていることが求められます。
このような基準を満たした事業所が、訪問看護サービスを提供しています。
訪問看護のサービス内容
訪問看護の具体的なサービス内容としては、主に下記の看護が挙げられます。
| サービス内容 | 概要 |
|---|---|
| 健康状態の観察とアドバイス | 血圧、体温、脈拍などのチェック |
| 日常生活のサポート | 排泄、入浴の介助、清拭、洗髪など |
| 医療処置 | 医師の指示による点滴、カテーテル管理、インスリン注射など |
| 医療機器の管理 | 在宅酸素、人工呼吸器などの管理 |
| ターミナルケア | がん末期や終末期でも自宅で過ごせるよう適切なケア |
| リハビリテーション | 拘縮予防、機能回復、嚥下機能訓練など |
| 認知症ケア | 事故防止や認知症介護の相談・工夫 |
| 介護指導・相談 | ご家族へのサポートやアドバイス |
上記のサービスの中から、一人ひとりの利用者の状況に合わせてケアマネジャーによってケアプランが作成され、プランに則り訪問看護サービスが提供されます。
訪問看護と訪問介護の違いとは
訪問看護は、医療的なケアや看護を目的としたサービスです。病状の観察、治療、リハビリテーション、薬の管理、医療機器の操作などを行います。0
一方、訪問介護は、日常生活の支援を目的としたサービスで、身体介護(入浴や排せつの介助など)や生活援助(食事の準備、掃除、洗濯などの家事)を提供します。
つまり、訪問看護は医療的なケア、訪問介護は日常生活のサポートを担当します。
訪問看護の利用条件
では、訪問看護サービスを受けるためにはどのような条件があるのでしょうか?
訪問看護を受けられる対象者は、主治医から訪問看護指示書を受けた人すべてが対象となります。
訪問看護を希望する場合は、受診している医療機関のほか、地域包括支援センターや訪問看護ステーション、介護保険・障害福祉窓口でも相談が可能です。
訪問看護を受ける際、患者となる人の条件により、介護保険と医療保険のどちらを利用できるかが異なります。
ちなみに、65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方(第1号被保険者)、または40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病」による要支援・要介護認定を受けた方につきましては介護保険が適用されます。
訪問看護のサービスを受けるためには、まずは受診している医療機関や地元の地域包括支援センター、訪問看護ステーションに相談しましょう。

介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
訪問看護にかかる費用
介護保険サービスを利用する時の自己負担費用は、基本的にサービス費用の1割です。
ただ、現役世代並みの所得のある方などは、2~3割負担の場合もあります。
費用はケアプランによって様々ですが、例えば、下記のケースで考えてみましょう。
【ケース:指定訪問看護ステーションを週3回の利用で、1回あたりの訪問時間は30分未満だった場合】
1回あたりの介護保険での点数は471点、これを週3回利用した場合、一か月では12回の利用となるので、471×12=5,652点
ここに、地域毎に物価等を考慮した10~11程度の単価を掛けます。
今回は簡素化のために10とすると、5,652×10=56,520円が一か月の訪問看護サービスの利用料となります。
ここで、今回のモデルケースの利用者が1割負担だった場合は1割を掛け、
56,520×1割=5,652円が自己負担金額となります。
上記はあくまでモデルケースであるため、これに加えて複数名の看護職員で訪問する場合や、緊急で訪問した場合等は追加でサービス利用料が発生します。
訪問看護のメリット
ビジネスパーソンにとって大きな助けとなる訪問看護のメリットを3つご紹介します。
【訪問看護のメリット】
- 在宅でありながら看護サービスを受けることができる
- 家族の負担も軽減できる
- 退院後に自宅療養に移行しやすい
在宅でありながら看護サービスを受けることができる
ご高齢になると、病院や診療所に定期的に通うだけでも大変です。電車やバスの乗り継ぎが必要になる方もいるでしょう。
そんな方にとって、訪問看護サービスは大きな助けとなります。
家族の負担も軽減できる
訪問看護サービスを利用できると、サービス利用者の家族も助かります。
病院への通院等があれば、その度に家族が有給休暇や介護休暇を取得しなければならない場合もあるでしょう。
その調整で苦労している家族にとっても、訪問看護サービスは大変ありがたいサービスでしょう。
退院後に自宅療養に移行しやすい
病院に入院していた方が無事に退院できても、その後の傷口の消毒やたん吸引に心配があると安心して暮らせませんね。
そんな方にも訪問看護サービスは助けになります。
定期的に看護師が自宅に様子を見に来てくれると、例え一人暮らしでも安心して暮らせます。
訪問看護のデメリット
利用者やその家族にとって大きな助けとなる訪問看護サービスですが、デメリットもご紹介します。
【訪問看護のデメリット】
- 掃除や料理等はサービスに含まれない
- 利用開始までに時間が掛かる可能性がある
- 介護保険の訪問看護は、支給限度額がある
掃除や料理等はサービスに含まれない
訪問看護サービスはあくまで利用者の方へ看護サービスを提供するものなので、日々の生活に必要な物品の買い出しや、調理、洗濯等は行いません。
そのため、そうしたサービスが必要であれば訪問介護サービス等の提供を受けるか、介護サービス外の実費負担のサービスを提供している業者と契約する必要があります。
利用開始までに時間が掛かる可能性がある
介護保険で訪問看護サービスの提供を受けるためには、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。
これまでに申請や認定を受けていなかった場合には、新規に申請する必要がありますが、認定を受けるまでに時間が掛かる可能性があり、それまではサービスを受けたくても受けることができません。
介護保険の訪問看護は、支給限度額がある
介護保険のサービスを利用する場合には、一人ひとりに支給限度額が設けられています。
原則1割負担の中で介護保険サービスを利用できるのはその支給限度額の中に限られるため、支給限度額を超えて発生した費用については、全額自己負担となります。
そのため、サービスを利用したくても経済的に利用できない可能性があります。
他の介護サービスとの違い
ここまで訪問看護サービスについて説明してきましたが、介護保険の他のサービスにはどのようなものがあるでしょうか?
訪問看護と連携できるサービスもあるかもしれません。そんな中で、介護保険の介護サービスで代表的な3事業について比較してみます。
デイケア(通所リハビリテーション)との違い
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 要介護者・要支援者が施設に通って訓練やリハビリを受ける介護サービス |
| 利用目的 | 運動機能訓練や口腔機能訓練を通して心身を健康に保ったり機能を回復させたりする |
| 利用対象者 | すべての要介護・要支援者 |
| 費用 | 原則1割負担で、1日あたりの利用時間の長さによって単価が変わる |
| 要介護度 | 要介護度1~5
要支援度1~2 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 専任の常勤医師1名 サービス利用時間を通して看護師や理学療法士などが1名以上(病院や介護老人保健施設の場合) |

デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイサービス(通所介護)との違い
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 介護サービスを提供している事業所に日中通いサービスの提供を受ける |
| 利用目的 | 身体機能の訓練を行ったり、他者と交流して孤立感の解消や認知症の予防を図る |
| 利用対象者 | すべての要介護・要支援者 |
| 費用 | 原則1割負担で、1日あたりの利用時間の長さによって単価が変わる |
| 要介護度 | 要介護度1~5
要支援度1~2 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 介護職員や看護職員、機能訓練指導員等のスタッフの配置基準があり |

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ショートステイとの違い
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| サービス内容 | 1日~30日までの短期間で施設に宿泊し介護や生活支援を受ける |
| 利用目的 | 介護者が自宅を留守にしたり、体調を崩した時などに利用することがある |
| 利用対象者 | すべての要介護・要支援者 |
| 費用 | 原則1割負担で、介護度や宿泊する居室のタイプによって異なり、食費等は自己負担となることがある |
| 要介護度 | 要介護度1~5
要支援度1~2 |
| スタッフ(所持資格の違い) | 介護職員や看護職員等のスタッフの配置基準があり |

「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
上記のように、名称が似ていてもその目的やサービス内容は異なっています。
訪問看護を選ぶときのポイント
訪問看護の事業所を選ぶときに気を付けるポイントとしてはどのようなものがあるでしょうか?
【訪問看護を選ぶポイント】
- 自宅からの近さ
- 働いているスタッフの数が十分かどうかや、専門職が在籍しているか
- 緊急時の対応が可能かどうか
- 主治医や地域の医療機関との連携ができているか
自宅からの近さ
やはりまずは自宅から近い訪問看護ステーション等の事業所はありがたいですね。
定期的な訪問に加え、緊急時にすぐに駆けつけてくれるという安心感は利用者にとっても家族にとっても助かります。
働いているスタッフの数が十分かどうかや、専門職が在籍しているか
働いているスタッフの数や専門職のスタッフがいるかどうかは、訪問看護の事業所毎に異なります。
例えば、働いているスタッフが看護師だけでは医療的なケアは可能ですが、摂食嚥下についての相談などはできません。
また、スタッフの人数が少なく、ぎりぎりの人員で運営している事業所では緊急時の対応ができない可能性があります。
そうした点で、スタッフの専門性や数は大事なポイントです。
緊急時の対応が可能かどうか
緊急時に連絡を入れてすぐに対応してくれるかどうかも大事なポイントです。
例えば、事業所が土日は休みなどで連絡が付かないタイミングがあるときには、別の緊急連絡先を用意しておく必要があります。
そうした理由から、緊急時の対応も確認しておくと良いでしょう。
主治医や地域の医療機関との連携ができているか
訪問看護の範囲内で対応できないような事態になったときに、すぐに主治医に連絡が付く体制が採られているかどうかや、地域の医療機関と連携ができていて、問題発生時にすぐに連絡が付く体制になっているかどうかも重要な確認ポイントです。
訪問看護を利用するまでの流れ
これまでを振り返り、訪問看護サービスを利用するまでの流れを確認していきます。
まずは地域包括支援センターやかかりつけの医療機関、地域の訪問看護ステーションに相談します。
その上で、まだ介護保険の申請を行っていない場合には市区町村に申請をし、介護認定審査会を経て認定を受けます。
続いて、基本的には相談を行って訪問看護ステーションや地域包括支援センターのケアマネジャーとケアプランについて相談をし、利用者の方のケアプランを作成します。
作成したケアプランに則り、訪問看護サービスやその他の介護サービスを受けながら利用者ご本人が望んだ生活をできる限り実現していきます。
ビジネスパーソンのみなさまへ
訪問看護サービスは、住み慣れた居宅で暮らしたいと願う、サービスを利用する本人やその介護に携わる家族にとって大きな助けとなるサービスです。
介護保険の制度には、分かりにくい部分もあるため、誰に相談すれば良いか分からない人もいるかと思います。
まずは地域包括支援センターや主治医、訪問看護ステーションに相談してみましょう。
そこに在籍しているケアマネジャーや社会福祉士等が相談に乗ってくれます。
高齢社会となることは避けられない日本で、ケアを受ける人もその家族もできる限り自分を大事できる、QOLの高い生活を送ってほしいと思います。

介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...