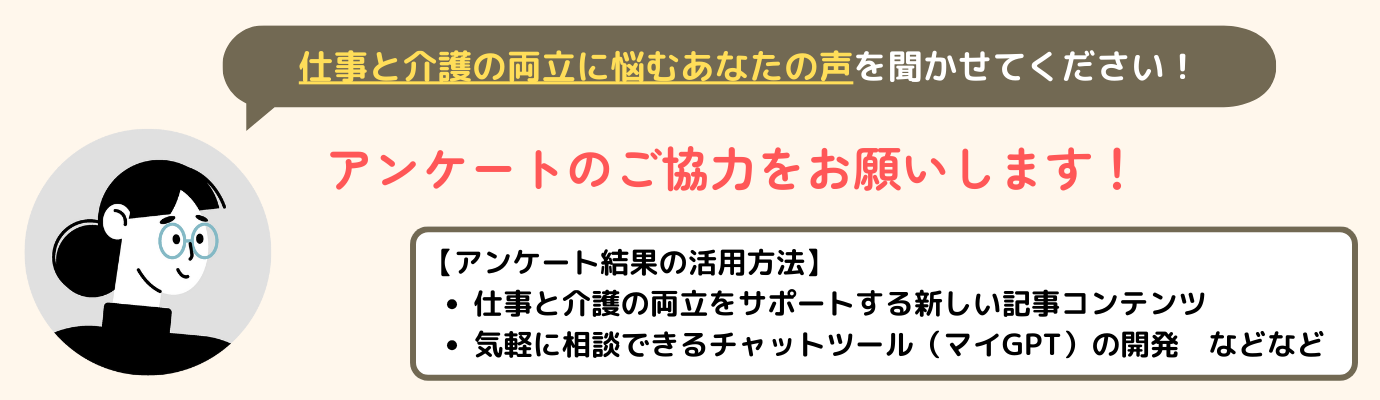訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。
利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。
ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します。
目次
訪問介護とは?
訪問介護とは、ホームヘルパーが利用者のご自宅に訪問して行う介護保険サービスです。
主に食事、入浴、排せつ、服薬などの『身体介護』や、調理、掃除、洗濯などの『生活援助』、通院の乗車や降車を含む外出サポートを行います。
訪問介護を利用できるのは、自宅で生活をしており、自分や家族だけで日常生活を送ることが難しい『要支援』認定者になります。
状態を悪化させないよう、利用者の自立した生活をサポートするのが訪問介護の目的になります。
訪問介護を提供するホームヘルパーは、介護福祉士もしくは定められた研修を修了した、いわゆる在宅介護を専門にしている人たちです。
介護保険法に基づく『訪問介護』の定義
訪問介護は、『介護保険法』に基づいて提供されるサービスです。
介護保険法は、介護や介護予防に必要な費用の給付額や、介護施設の運用基準について定めています。
つまり、介護が必要な高齢者とその家族を、社会全体で支える仕組み(介護保険制度)の土台だと言えるでしょう。
この介護保険法において、『訪問介護』は以下のように定義されています。
【介護保険法 第8条2項】
2 この法律において『訪問介護』とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下『有料老人ホーム』という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下『居宅要介護者』という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。
引用:e-Gov法令検索『介護保険法 第8条2項』
つまり、介護保険で利用できる『訪問介護』サービスは、介護支援専門員が行う、入浴、排せつ、食事などの介護や、その他の日常生活で必要なサポートです。
利用者は自宅にいること、また要介護者であることが必須条件となります。
また、訪問介護を運営する基準は、介護保険法により「手続きの内容説明」から「会計区分」に至るまで細かいルールが設定されています。
例えば、訪問介護を行う人員は、「利用者35人に対して1人」が基準です。
訪問介護のサービス内容とは?
訪問介護のサービス内容は、直接身体に触れて行う『身体介助』と、生活に必要な家事を支援する『生活援助』の大きく2つに分けられます。
それぞれの主なサービス内容は、以下の通りです。
| 身体介助 | 生活援助 |
|---|---|
| 食事介助 | 料理 |
| 清拭 | 買い物 |
| 排泄介助 | 洗濯 |
| 更衣介助 | 掃除 |
| 体位変換 | ゴミ出し |
| 移乗介助 | 薬の受け取り |
| 外出介助 | ベットメイク |
上記の他にも、通院の際の送迎、車の乗り降り介助を行う『通院等乗降介助』があります。いわゆる『介護保険タクシー』がこれに相当します。
訪問介護の利用条件
訪問介護サービスを受けるには、以下の条件を満たしている必要があります。
・自宅で生活をしており、要介護1~5の認定を受けた方
ここでの自宅には、健康型有料老人ホームや住宅型老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、「介護サービスが提供されていない施設」も含まれます。
ただし、特別養護老人ホームや介護老人施設など、施設内で介護サービスが受けられる場合は、訪問介護の対象外となります。
訪問介護と介護予防訪問介護の違いとは
訪問介護は要介護者を対象としており、利用者を世話することが目的です。
これに対して介護予防訪問介護は要支援者が対象であり、その目的は世話ではなく「支援」です。
介護予防訪問介護は、要介護への状態悪化を予防するのが目的の支援になり、
利用回数にも制限が設けられており、要支援1の方は週1回まで、要支援の2の方は週3回まで使えます。
訪問介護にかかる費用
訪問介護にかかる費用は利用時間によって変わります。「生活援助を45分」など、事前に頼む内容と時間を決めておくと、有効に活用できるでしょう。
訪問介護利用時の費用の内訳
訪問介護(ホームヘルパー)の利用料金は、以下の4つの要素で構成されています。
| 利用料金 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 身体介護、生活援助、通院等乗降介助の3種類に分かれ、それぞれ料金設定が異なります。 |
| 利用時間 | サービス内容ごとに設定された時間単位に基づいて料金が決まり、時間が長くなるほど料金は高くなります。 |
| 負担割合 | 原則1割負担ですが、所得に応じて2割または3割負担となる場合があります。 |
| 加算 | 利用状況により、基本料金に上乗せして料金が加算されることがあります。 |
要介護1~5の認定を受けた方(利用者負担が1割の場合)の、利用時費用の内訳は以下の通りです。
| サービス費用の設定 | 利用時間 | 利用者負担(1割) (1回につき) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 20分未満 | 165円 |
| 20分以上30分未満 | 248円 | |
| 30分以上60分未満 | 394円 | |
| 60分以上 | 575円 | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 181円 |
| 45分以上 | 223円 | |
| 通院時の乗車・降車等介助 | 98円 |
※参照: どんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ) | 公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索『介護サービス情報公表システム』
サービスの提供時間によって、訪問介護の利用料金が変わります。身体介護は4段階、生活援助は2段階の加算形態に分けられています。
なお、通院時の乗車、降車の介助は1回あたりの費用です。
月額費用の内訳
1日あたりの訪問介護にかかる費用は、「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」で計算ができます。
例えば、要介護3の利用者が、1日50分の身体介助を週5回利用した場合の月額費用は、
・396円×5回×4週=7,920円
です。
なお、早朝(6~8時)や夜間(18~22時)利用した場合は25%、深夜(22時~6時)に利用した場合は50%増しの金額がかかります。
自己負担額
訪問介護は介護保険制度が適用されるので、65歳以上の介護保険の自己負担額は、基本的に1割と考えてよいでしょう。
ただし、一定以上の所得がある場合は2〜3割の負担になるなど、合計所得金額(年金収入+それ以外の収入)によって変動があります。
また、もしも利用頻度が高く自己負担額が高額になる場合には、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度なども利用できるのでご安心ください。
訪問介護のメリットは?
訪問介護を利用するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは訪問介護のメリットを4つご紹介します。
【訪問介護のメリット】
- 自宅での生活を続けながら介護を受けられる
- 介護施設に入所するよりも費用を抑えられる
- 個別の対応をしてもらえる
- 利用したいときだけ利用できる
メリット①自宅での生活を続けながら介護を受けられる
訪問介護最大のメリットは、自宅での生活を維持したまま介護を受けられる点です。高齢になっても自宅から離れたくない方は非常に多いと思います。そのような方にとって訪問介護は最適なサービスです。
メリット②介護施設に入所するよりも費用を抑えられる
介護施設に入所する場合は、初期費用としてまとまった金額が必要になり、月額費用も安くはありません。一方、訪問介護では『利用分だけ料金を支払う』ので、予算をコントロールでき、費用を抑えることが可能です。
メリット③個別の対応をしてもらえる
訪問介護は、状況に合わせて利用したいサービスを選択できるなど、個別に柔軟な対応をしてもらえます。
反対に、大勢の方が入所する介護施設では、できることとできないことが明確に分けられている場合が多いでしょう。
メリット④利用したいときだけ利用できる
訪問介護は、必要なときに必要な分だけ頼むことが可能です。
そのため、費用を抑えられるだけでなく、
- 家族に急な仕事が入った
- 明日病院に行かなければならなくなった
といった際の急な依頼にも対応をしてもらえます。
訪問介護のデメリットは?
反対に、訪問介護にデメリットはあるのでしょうか?ここでは訪問介護を利用するデメリットを3つご紹介します。
【訪問介護のデメリット】
- 受けられないサービスがある
- ホームヘルパーと相性が合わないことがある
- 自宅に他人を入れなければならない
デメリット①受けられないサービスがある
柔軟な対応をしてもらえる訪問介護ですが、受けられないサービスもあります。
直接利用者の援助に当たらないサービスは、提供できない決まりだからです。
例えば、利用者の家族分の家事や、子どもの世話、利用者以外の部屋の掃除や来客対応などは提供ができません。
デメリット②ホームヘルパーと相性が合わないことがある
利用者とホームヘルパーが一緒にいる時間が長いため、どうしても相性が合わない可能性が出てきます。
そういった場合は、ケアマネジャーにホームヘルパーの担当替えの依頼を検討しましょう。
デメリット③自宅に他人を入れなければならない
訪問介護を受けるためには、自宅に他人を入れなければなりません。
他人を自宅に入れることにストレスを感じる方には、訪問介護は合わない可能性があります。
訪問介護以外の介護サービス
| 介護サービス | サービス内容 | 提供するスタッフ |
|---|---|---|
| 訪問介護 | 自宅での身体介護
生活援助等 |
ホームヘルパー、ケアマネジャー等 |
| 訪問看護 | 自宅での医療処置
療養上の世話等 |
看護師、准看護師、保健師等 |
| デイケア | 施設でのリハビリ
医療的ケア 日常生活介護等 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等 |
| デイサービス | 施設での健康チェック
日常生活支援等 |
介護福祉士、介護支援専門員等 |
| ショートステイ | 入所施設での日常生活支援等 | 介護福祉士、介護支援専門員等 |
訪問介護と似たサービスに、『訪問看護』『デイケア』『デイサービス』『ショートステイ』などがあります。それらの類似サービスについてご紹介します。
訪問看護とは?
訪問看護は、看護師または准看護師、保健師が、利用者の自宅を訪問して、医療処置や療養上の世話を行うサービスです。訪問看護の目的は、家庭での生活と治療の両立になります。
また、利用できるのは原則として要支援・要介護認定を受けている65歳以上の方です。20分未満で比較すると313円で、訪問介護のほぼ倍程度の費用がかかります。

高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
デイケアとは?
デイケアは、『通所リハビリテーション』へ通って利用するサービスです。
利用者の心身機能の維持・回復を目的として、医師の指示のもとに行われるリハビリ、医療的ケア、日常生活介護を受けられます。
要支援・要介護の認定を受けた高齢者が利用でき、リハビリは理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が提供します。費用は、要介護3の方で1回につき924円です。

デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイサービスとは?
デイサービス(いわゆる通所介護)は、デイサービスセンター等で提供されるサービスです。
日帰りで健康チェックや昼食、入浴といった日常生活支援を受けられ、利用者の心身機能の維持や向上、家族の負担軽減を目的に利用できます。
対象者は、要支援・要介護の認定を受けた高齢者です。要介護3の方であれば1回あたり883円で利用できます。

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ショートステイとは?
ショートステイは、ショートステイ専門の施設や入所施設で介護保険サービスを受けられるものを指します。
自宅での生活は難しいけれど入院するほど健康状態が悪くない場合や、介護をしている家族が一時的に家を空けるとき、利用者と家族の両方が自宅での暮らしを続けるために利用できます。
利用対象者は要支援・要介護認定を受けた方です。費用は入所施設や期間によってさまざまです。

「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
「仕事で遠方に出張に行くことになった」 「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」 「体調を崩してしまった」 こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。 ショートステイを利用すれば、要介護...
訪問介護を選ぶときのポイント
訪問介護を頼むことを決めたなら、次にすべきなのは訪問介護選びです。ここでは、利用者に合った訪問介護を選ぶポイントについて紹介します。
【訪問介護を選ぶポイント】
- 利用者の希望を聞く
- 複数の施設を比較する
- 直接担当の人と会う
ポイント①利用者の希望を聞く
訪問介護は訪問介護スタッフが居宅に訪問することになります。
利用者本人に安心してサービスを受けてもらうためには、どんな人に来てもらいたいか、どんなサービスを受けたいかなどを、事前に話し合っておくことが重要です。
また、本人の病気や身体の状況によって、今後どのようなサービスが必要になるかを想定して、希望サービスに組み込むことも検討しましょう。
ポイント②複数の施設を比較する
Webサイトやパンフレットを使って、住んでいる地域にある訪問介護事業者の情報を、できるかぎり集めます。
その際、費用面はもちろん、利用できるサービス、営業時間などを比較してください。
特に、希望しているサービスが提供されているかどうかのチェックは必須です。
土日の利用を検討している場合は、営業時間の確認も忘れないようにしましょう。
ポイント③直接担当の人と会う
ピックアップしたした訪問介護施設事業者の担当者とは、直接会って説明を受けてみてください。
そこで、契約書や重要事項、費用の説明があるか、希望するサービスが受けられるか、担当者の変更ができるかなど、気になることはすべて確認してみましょう。
担当者の態度や口調なども確認し、利用者との相性が合うかもチェックするのがおすすめです。
訪問介護を利用するまでのステップ
訪問介護を利用するまでには、どのような申請や手続きが必要なのでしょうか?ここでは訪問介護を利用するまでのステップを紹介します。
ステップ①要介護認定の申請
訪問介護の利用には、要介護の認定が必要です。介護認定申請書へ記入をし、住んでいる市区町村の介護保険関係の窓口で申請をしましょう。
原則は本人の申請になりますが、難しい場合は家族や地域包括支援センターなどの申請代行も可能です。
ステップ②介護認定の通知
介護認定調査員による自宅での介護調査後、30日以内に介護サービスを利用する本人宛に認定通知が郵送されます。
そこで認定された要介護状態区分は、申請日にさかのぼって効力が生じます。
ステップ③介護支援専門員の決定・ケアプラン作成
利用者が要介護1以上の場合は、ケアマネジャーの選定を居宅介護支援事業所に依頼してください。
そこで決定したケアマネジャーが利用者の自宅へ訪問して面談します。面談での情報を鑑みて、ケアマネジャーが『ケアプラン』を作成します。
ステップ④事業者の選定・契約
決定したケアプランを基に、サービスを提供してもらう訪問介護事業所を選び、契約をします。
契約後に、訪問介護サービスが開始となります。
ビジネスパーソンのみなさまへ
この記事では、『訪問介護』について、主に以下のご紹介をしました。
- 訪問介護のサービス内容:訪問介護には、身体介護と生活支援があります。
- 訪問介護の利用条件:要支援または要介護の認定を受けた方が利用対象者です。
- 訪問介護にかかる費用:基本的に自己負担額は1割です。1日当たり「サービスの種類別料金 × 利用時間 + その他料金(加算)」で計算ができます。
- 訪問介護を利用するまでのステップ:訪問介護を利用するためには、要介護認定の申請、ケアマネジャーの選定依頼、事業者との契約が必要です。
訪問介護は、要支援・要介護認定を受けた高齢者と家族が、自宅で自立した生活を送るサポートをするサービスです。
利用者ご本人が住み慣れた家を離れたくない場合や、費用を抑えながら家族の介護負担を減らしたい場合、ぜひ利用を検討してみてください。