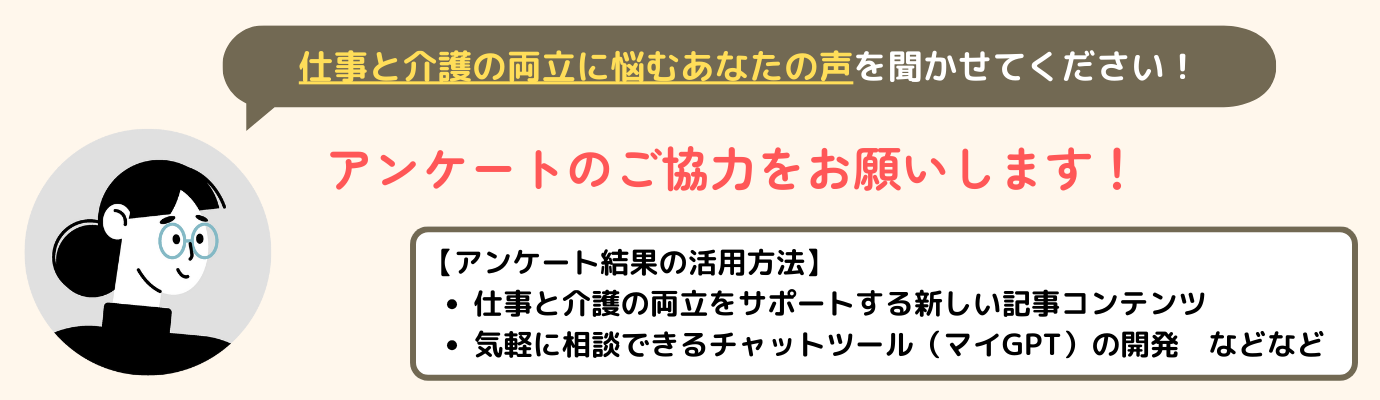「仕事で遠方に出張に行くことになった」
「冠婚葬祭で外出しなければならなくなった」
「体調を崩してしまった」
こんなとき、自宅で介護をする介護者は、一時的に介護ができなくなってしまいます。そんな、いざという時に頼れるサービスが、ショートステイです。
ショートステイを利用すれば、要介護者の介護と介護者の外出・休息が両立できるだけでなく、介護をレスパイトする(一休みする、息抜きをする)ことで、介護者の心と身体がリフレッシュされるというメリットもあります。
ここでは、ショートステイのメリットを理解し、安心して利用できるよう、サービス内容の詳細から実際に利用を始めるまでを解説します。
目次
ショートステイとは?
ショートステイとは、要介護者(利用者)を短期間、受け入れてくれるサービスです。入浴や排泄、食事などの介護サービスや日常生活上の支援、機能訓練などが受けられます。
要支援者・要介護者が自宅で自立した日常生活を送れることを目的としてサービスが提供されます。最短1日から施設に宿泊ができ、連続して最長30日まで利用可能です。
ショートステイを利用することで、要支援者・要介護者の自宅でのひきこもりによる孤立感の解消や心身機能の維持・回復だけでなく、介護者の負担も軽減されます。
また、たとえばビジネスパーソンのみなさまが在宅で介護をしている場合、介護をする方が体調を崩したり、急な冠婚葬祭や出張などにより介護をできなくなるケースもあると思われます。
このように一時的に在宅介護が難しくなる場合などに活用できるサービスなのです。
ショートステイには、大きく分けて、短期入所生活介護、短期入所療養介護、それ以外のショートステイの3種類があります。
このうち、介護保険が適用されるショートステイは、短期入所生活介護と短期入所療養介護です。自立されている方についてはこれらのショートステイを利用することができません。
ただし、有料老人ホームなどで提供される介護保険適用外のショートステイについては利用できるところがあります。
短期入所生活介護については特別養護老人ホームや一部の有料老人ホームが運営、短期入所療養介護については介護老人保健施設や介護医療院、介護保険外のショートステイについては、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅により運営されています。
介護保険法での定義
介護保険法によると、介護保険が適応されるショートステイは以下のように定義されています。
【介護保険法 第八条 9】
この法律において『短期入所生活介護』とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
【介護保険法 第八条 10】
この法律において『短期入所療養介護』とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
以上の内容をまとめると、
短期入所生活介護サービスとは、利用者の心身の機能の維持、利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るサービスです。
利用者が可能な限り自宅で、自立した日常生活を営むことができるようなサービスが提供されます。
利用者は介護老人保健施設や特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。
一方、短期入所療養介護サービスとは、療養生活の質の向上、利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るサービスです。
利用者が可能な限り自宅で、自立した日常生活を営むことができるようなサービスが提供されます。
短期入所生活介護サービスと異なり、看護的、医学的管理の下で、介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話が行われます。
さらに、運営するために必要な職員や設備、人員などの各サービスの運営基準も、短期入所生活介護・短期入所療養介護でそれぞれ規定されています。
※参考:厚生労働省 短期入所生活介護及び 短期入所療養介護 (参考資料)
ショートステイのサービス内容
ショートステイでは、日常生活を営むことを目的として、以下の介護サービスが受けられます。
- 食事介助
- 入浴介助
- 排泄介助
- リハビリテーション、レクリエーションなどの機能訓練
ショートステイ利用時は介護保険が利用できます。
介護保険で利用できる介護サービスは、既に述べたように、「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類があります。
短期入所療養介護では、看護・医学的な管理が加わります。
| 短期入所生活介護 | 短期入所療養介護 |
|---|---|
|
|
ショートステイの入居条件
介護保険が適応される場合は、要支援1・2、要介護1〜5の要介護認定を受けた人が利用できます。
介護保険が適応されない施設では、要支援、要介護の状態でなくとも利用可能です。
| 介護保険が適応されるショートステイ | 介護保険が適応されないショートステイ |
|---|---|
|
(いずれの費用も全額自己負担) |
※特定疾病:
加齢に伴う心身の変化によって生じ、要介護状態の原因であると医学的に認められる疾病のこと。介護保険施行令第2条で定められた16種類の病気を指す(下記参照)。
次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案される。
(1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
(2) 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
| 【特定疾病の範囲】 |
|---|
| 1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※ |
| 2. 関節リウマチ※ |
| 3. 筋萎縮性側索硬化症 |
| 4. 後縦靱帯骨化症 |
| 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 |
| 6. 初老期における認知症 |
| 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※ |
| 【パーキンソン病関連疾患】 |
|---|
| 8. 脊髄小脳変性症 |
| 9. 脊柱管狭窄症 |
| 10. 早老症 |
| 11. 多系統萎縮症※ |
| 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
| 13. 脳血管疾患 |
| 14. 閉塞性動脈硬化症 |
| 15. 慢性閉塞性肺疾患 |
| 16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)
出典:特定疾病の選定基準の考え方 厚生労働省
ショートステイにかかる費用
ショートステイ利用時の費用は、介護保険の適応部分と適応外部分に分かれます。
介護保険が適用されるのは、介護サービスにかかる利用料金のみです。
| 保険対象 | 費用項目 | 要素 |
|---|---|---|
| 介護保険内 | 基本料金 | ① 要介護度 |
| ② 施設の種類 | ||
| ③ 部屋のタイプ | ||
| ④ 滞在日数 | ||
| 特別サービス利用分の加算 | ||
| 介護保険外 | 食費・居住費 | 有料老人ホームなどの全額自己負担のショートステイ |
自己負担額
| 費用分類 | 要素 | 詳細 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要介護度 | 要介護度が高いほど高額になります。 |
| 施設の種類 | 併設型、単独型の2種類があります。
|
|
| 部屋のタイプ | 多床室、従来型個室、ユニット型があります。
|
|
| ユニット型 | 約10人を1つのユニットとしてサービスが提供されます。
台所、食堂、浴室は共用で、居室自体は個室です。 |
|
| 滞在日数 | 長期滞在ほど高額になります。
入所日や退所日も滞在日数に含まれるため、費用が発生しますので、注意が必要です。 |
|
| 特別サービス利用分の加算 | 以下「特別サービス利用分の加算」で解説します。 | |
| 介護保険外の費用 | 食費・居住費などは全額自己負担となります。
有料老人ホームなどの全額自己負担のショートステイもあります。 |
入居時の費用の内訳(介護保険適応内)
● 基本料金
【<短期入所生活介護 併設型(特別養護老人ホームなど)>の場合】
| 多床室 | 従来型個室 | ユニット型 (個室、多床室) |
|
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 446円/日 | 446円/日 | 523円/日 |
| 要支援2 | 555円/日 | 555円/日 | 649円/日 |
| 要介護1 | 596円/日 | 596円/日 | 696円/日 |
| 要介護2 | 665円/日 | 665円/日 | 764円/日 |
| 要介護3 | 737円/日 | 737円/日 | 838円/日 |
| 要介護4 | 806円/日 | 806円/日 | 908円/日 |
| 要介護5 | 874円/日 | 874円/日 | 976円/日 |
【<短期入所療養介護 介護老人保健施設(老健)>の場合】
| 見出し | 多床室 | 従来型個室 | ユニット型 (個室、多床室) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 610円/日 | 577円/日 | 621円/日 |
| 要支援2 | 768円/日 | 721円/日 | 782円/日 |
| 要介護1 | 827円/日 | 752円/日 | 833円/日 |
| 要介護2 | 876円/日 | 799円/日 | 879円/日 |
| 要介護3 | 939円/日 | 861円/日 | 943円/日 |
| 要介護4 | 991円/日 | 914円/日 | 997円/日 |
| 要介護5 | 1045円/日 | 966円/日 | 1049円/日 |
※ 「介護報酬の算定構造」(厚生労働省・2021年4月)に基づき計算。
※ 上記は目安の金額であり、市区町村や介護・看護体制などで費用は異なります。
※ 上記は自己負担が1割の場合の金額です。所得により自己負担は2割〜3割となり、自己負担額は上記の2〜3倍になります。
●特別サービス利用分の加算
専門的なサービスや、より充実したサービスを提供する施設では、下記のような加算がある場合があります。
このようなサービスは、施設を選ぶ基準となりますが、プラスの費用がかかります。
個々のサービス費用はそれほど高額ではありませんが、積み重なると高額になります。施設毎のサービスを比較し、必要なものを充分に検討しましょう。
【特別サービス利用分の加算例】
- 個別機能訓練加算(計画書に基づいて個別に機能訓練を提供した場合の加算)
- 専従機能訓練指導員配置加算(常勤専従の機能訓練員を配置した場合の加算)
- 緊急短期入所受入加算
- 医療連携強化加算
- 看護体制加算
- サービス提供体制加算
- 送迎加算
- 療養食加算
- 夜勤職員配置加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
など
その他費用の内訳(介護保険適応外)
食費および居住費(部屋代)は全額自己負担となります。
料金は施設により、異なりますが、世帯年収により、公費補助があり、条件を満たせば軽減制度を利用できます。(「特定入所者介護サービス費」や「高額介護サービス費」など)。
これらは、世帯年収や利用料金などで条件が決まっているため、お住まいの自治体で確認してみましょう。
また、これら以外に、レクリエーション費用などがかかる施設があります。
ショートステイのメリットは?
ショートステイを利用するメリットおよびデメリットを下記にまとめました。
【ショートステイのメリット】
- 介護疲れや負担の軽減につながる
- 介護者の急な外出が可能となる
- 気分転換につながる
- 心身機能の回復・維持・向上を図れる
- 施設のスタッフや他の利用者との交流を楽しめる
メリット①:介護疲れや負担の軽減につながる
最大のメリットは、介護者の負担の軽減です。
介護により、身体的、精神的に余裕が無くなることも多く、介護疲れも社会問題となっています。
ショートステイを利用することにより、介護者が休息を取る=レスパイトできます。
ショートステイを利用することで、日々の疲れとストレスが解消され、在宅介護を続ける活力も生まれていくことでしょう。
メリット②:介護者の急な外出が可能となる
ショートステイの利用により、介護者の急な出張や冠婚葬祭での外出が可能となります。
メリット③:介護者の気分転換につながる
体調を崩したとき、旅行するときに利用することで、心身の休息、リフレッシュができます。
また、平日にショートステイを利用し、休日は自宅で介護をすれば、仕事と介護の両立も可能となります。
メリット④:利用者の心身機能の回復・維持・向上を図れる
病院を退院後に利用すれば、自宅での生活に戻る前に、生活リズムを整えられます。
さらに、リハビリを行うことで、退院後の心身機能を回復・維持・向上できます。
メリット⑤:施設のスタッフや他の利用者との交流を楽しめる
将来、施設への入居を検討している要支援・要介護者が、ショートステイの利用により、介護専門施設を体験できます。
どのような介護サービスを利用できるのか、どのような人が利用しているのかなどを知る、よい機会となります。
ショートステイのデメリットは?
ショートステイ利用希望者が多いこと、利用により要支援・要介護者の生活環境が大きく変わることなどから生じるデメリットがあります。
【ショートステイのデメリット】
- 予約が取りにくい
- 要介護者にとって新しい環境への適応が難しい
- 連続利用は上限が30日
デメリット①:予約が取りにくい
ショートステイの利用希望者は多いため、予約が取りにくいかもしれません。
加えて、急な用事により、急遽、利用が必要となることもあります。自宅で介護をしている方は、普段から利用可能な施設をチェックしておき、空き状況を確認しておくとよいでしょう。
デメリット②:利用者にとって新しい環境への適応が難しい
要支援・要介護者にとっては、生活環境が大きく変わり、ストレスや不安を感じやすくなります。
特に認知症を発症している方は、環境の変化を苦手とする場合が多く、ショートステイに抵抗を感じる方もいらっしゃいます。
デメリット③:連続利用は上限が30日
同じ月内、月またぎ、いずれの場合も、利用は連続して30日までという制限があります。
連続として数えられないのは、下記の2つのみです。
- 他のサービスに入所する
- 一度、自宅に帰宅する(30日目に帰宅。次の日は自宅で過ごし、その次の日から利用可能。)※30日目・31日目に別の事業所のショートステイに入所した場合でも、ショートステイの連続利用として数えられます。
他の介護施設サービスとの違い
ショートステイとデイサービス、デイケアの違いは、利用時間、時間帯および利用目的(各施設の注力ポイント)です。
| 見出し | ショートステイ | デイサービス | デイケア |
|---|---|---|---|
| 利用時間 | 短期入所 日中、宿泊有り |
日中のみ | 日中のみ |
| 日中のサービス | 昼食や入浴、レクリエーションが中心 | 昼食や入浴、レクリエーションが中心 | 専門的なリハビリや健康管理などの医療的サポートが中心 |
| 注力ポイント | 要支援・要介護者が自宅で自立した日常生活を送れることを目的とする |
|
|
デイサービスとの違い
ショートステイは日中の利用に加え、短期入所による宿泊がありますが、デイサービスは、日中の利用のみとなります。日中のサービスは、昼食や入浴、レクリエーションなどで、両サービスで大きな差はありません。
ただし、ショートステイはすでに入居している利用者と同じペースでスケジュールが進むため、時間配分にゆとりがあります。
宿泊を伴う旅行に行く場合はショートステイ、日中の介護の負担軽減や一時的に外出したい場合はデイサービスといったように、利用したいタイミングを考慮して、どのサービスを利用するかを決めるとよいでしょう。

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
デイケアとの違い
ショートステイのサービス目的は、要支援・要介護者が自宅で自立した日常生活を送れるように支援することで、日常生活の介護に力を入れています。
一方、デイケアのサービス目的は、身体機能の回復・維持、日常生活の回復、認知機能の改善で、リハビリなどの医療的ケアに力を入れています。
近年、機能訓練が受けられるデイサービスや日常生活介護サービスを受けられるデイケアも増えています。

デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。 自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。 そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。 本記事では、デイケアのサービス内容や費...
ショートステイを選ぶときのポイント
特にチェックしておきたいのは、食事介助の様子、介護職員の対応です。
可能であれば、ショートステイを利用する前に施設を見学しておくとよいでしょう。
【ショートステイを選ぶときのポイント】
- 入居者の様子
- 食事介助
- レクリエーション
- スタッフの様子
- 建物や部屋の清掃状況
ポイント①:入居者の様子
入居者の下記の様子を確認しましょう。
- 入居者の表情はどうか
- 入居者はどのように過ごしているか
既に入居している利用者の方々に、笑顔や安心したような表情が見られるかなどがチェックポイントです。
ポイント②:食事介助
食事介助の下記ポイントを確認しましょう。
- メニューに偏りはないか
- 食事量は適切か
- 1人のスタッフが一度に複数の利用者の食事介助をしていないか
- 利用者の食べるペースを無視して食べさせたりしていないか
ポイント③:レクリエーション
レクリエーションについて下記ポイントを確認しましょう。
- どのような内容か
- 参加者の表情や職員の取り組む姿勢はどうか
- 行われている頻度
- 参加を嫌がる利用者がいるか、嫌がる利用者への対応はどうか(無理強いはしていないか)
- 誘導方法はどのように行っているか(無理強いにならない程度に、参加誘導の努力はしているか)
ポイント④:スタッフの様子
下記のようなポイントでスタッフの様子を見ましょう。
- どのような対応をしているのか
- 表情や態度はどうか
- 言葉遣いや挨拶はどうか
- スタッフの教育レベルはどの程度か
- スタッフ同士のコミュニケーション、職種間の連携が取れているか
ポイント⑤:建物や部屋の清掃状況
建物や部屋の状況について、下記ポイントで確認しましょう。
- 利用者が快適に過ごせているか
- 部屋は使いやすいか
- 清潔感はあるか(衛生管理が整っているか)
- 整理整頓されているか(転倒などのリスク意識はあるか)
- 施設内の臭いはどうか(汚物処理対応の状況)
ショートステイへの入居から退去までの流れ
4日以上連続してショートステイを利用するには、要介護認定を受けた後、ケアマネジャーがケアプランを作成します。
ケアプラン作成後、利用したい施設を選び、契約へと進みます。
介護者に急用がある場合や4日未満の短期入所であれば、ケアプランなしでショートステイが利用可能です。
また、介護保険適用外の有料ショートステイを利用する場合は、該当施設へ直接に相談します。要介護度や年齢による制限はありません。
【STEP.1】要認定介護を受ける
自治体に要介護認定を申請し、介護認定調査員による認定調査を受けます。
申請から30日以内に認定結果が届きます。認定が決定した後、認定結果通知と介護保険被保険者証を受領します。
自立、要支援1〜2と認定された場合は地域包括支援センターへ、要介護1〜5と認定された場合は居宅介護支援事業所へ連絡します。
【STEP.2】ケアマネジャーに相談する
要支援者、要介護者のいずれにも、ケアマネジャーが作成するケアプランが必須となります。ケアマネジャーはケアプラン作成に加え、利用の申し込みも代行してくれます。
介護保険適応外のショートステイを利用したい場合は、ケアマネジャーへの連絡は不要です。
【STEP.3】利用したいショートステイ施設を選ぶ
利用したいショートステイ施設の空き情報を確認し、利用する施設を検討します。
年末年始、ゴールデンウイークなどは予約が取りにくいこともあるため、早めにスケジュールを調整しておくとよいでしょう。
【STEP.4】利用申し込み
利用する施設が決まったら、ケアマネジャーが利用者ご本人の病状や心身状態を判断するための必要書類を作成します。必要書類が作成された後、介護サービス事業者(ショートステイ施設)に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示し、ケアプランに基づいた施設サービスの利用が可能となります。
【STEP.5】契約
利用にあたっての重要事項の説明を受け、説明内容に同意したのちに契約を結びます。
契約後、利用する日程、利用時に持参する物などを確認し、利用開始となります。
なお、ケアプランに基づいた利用者負担は、所得に応じて自己負担割合が異なります。基本的に費用の1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担となります。
ビジネスケアラーのみなさまへ
ショートステイは、利用者が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるようにすることを目的とし、同時に、孤立感の解消や心身機能の回復・維持・向上を目指すサービスです。
また、家族の介護の負担を減らし、介護者の生活や仕事との両立を図るサービスでもあります。
一方、利用者にとっては、慣れない場所での生活、宿泊となり、不安や心配もあることでしょう。
利用を検討するときは、まず、ケアマネジャーに相談してみましょう。
そして、実際にいくつかの施設を訪問、見学してみてください。実際に施設の様子を目にすることで、利用することになった際にも、心に余裕をもって利用できるでしょう。
利用者の介護、機能向上のみならず、介護者の心と身体の負担の軽減も可能となるショートステイを、どうか上手に利用してください。