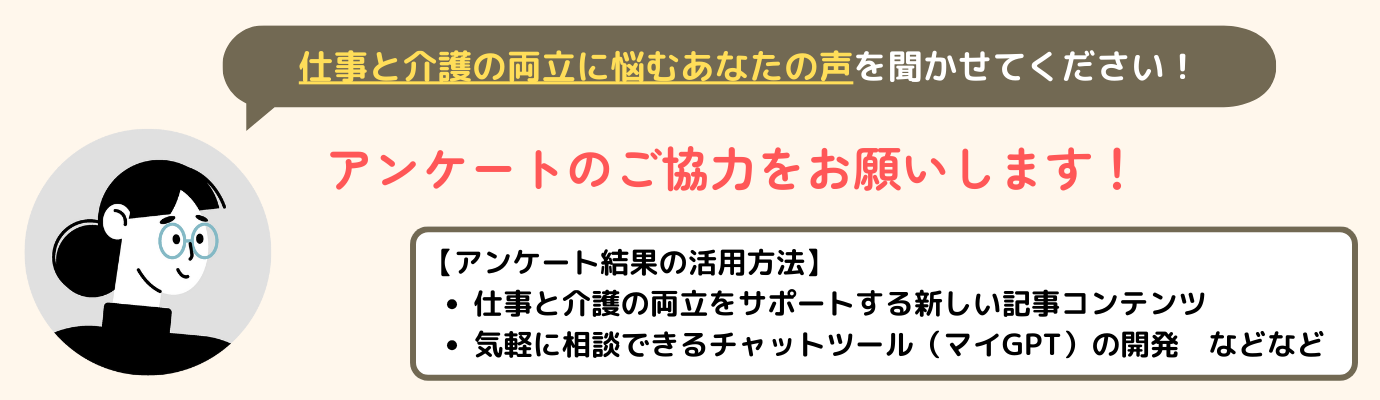デイケア(通所リハビリテーション)は、リハビリや医療ケアに特化した通所型の介護サービスです。
自宅で介護をしようにも、専門的なリハビリが必要なために対応に悩む例は少なくありません。
そのような場合は、デイケアの利用を検討するのも良いと思われます。
本記事では、デイケアのサービス内容や費用、利用までの流れなどを解説します。
デイケアのメリットや選び方のポイントを知り、利用者に合った施設選びの参考にしてください。
目次
デイケア(通所リハビリテーション)とは?
デイケア(通所リハビリテーション)は自宅で暮らす要介護・要支援者向けの介護保険サービスです。
介護老人保健施設や介護医療院、病院、診療所などの施設に日帰りで通い、医師の指導のもと専門職によるリハビリを受けられます。
「デイサービス(通所介護)」と比べると、デイケアはリハビリに特化してるといえるでしょう。
デイケアには専任の常勤医師が配置されているのが特徴的です。
他には看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護職員などが在籍。
設備も充実した環境で、医療に特化したサポートを提供しています。
デイケアの主な役割はリハビリによる心身機能の維持・向上ですが、必要に応じて食事や入浴、排せつなどの介助にも対応します。
他の利用者や施設職員とのコミュニケーションの機会が増える他、家族の介護負担を軽くするメリットも期待できるでしょう。
介護保険法での定義
デイケアは介護保険法で次のように定義されています。
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
デイケアはリハビリに特化したサービスのため、利用するには主治医からリハビリが必要だと診断してもらうのが前提です。
ちなみに、厚労省の調査によると、「脳卒中」と「骨折」が原因でデイケアに通う例が特に多いというデータがあります。
専門的なリハビリや医療ケアを提供するために、デイケアでは施設で働く職員体制の基準が定められています。
そのポイントを以下にまとめました。
【専任の常勤医師がいる】
デイケアの大きな特徴が、医師の指示のもとでリハビリを行う点です。そのため、施設には専任の常勤医師を1人以上配置しなければなりません。
ただし、施設が病院や診療所と併設されている場合は兼務してもいいことになっています。
【従事者の人数】
デイケアでは医師の他に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員などが働いています。リハビリ単位ごとに、利用者10人に対し1人以上の従事者を配置する決まりです。
その中でも、専門の国家資格を持つ理学療法士や作業療法士、言語聴覚士は、リハビリ単位ごとに利用者100人に対して1人以上の配置が義務付けられています。
※(参考:厚労省資料「通所リハビリテーション」)
デイケアのサービス内容
実際にデイケアを利用した場合、どのようなサービスを受けられるのでしょうか。主な例をいくつか紹介します。
| サービス内容 | 詳細 |
|---|---|
| リハビリ | リハビリを開始する前に、利用者それぞれの心身の状態や要望を踏まえた目標を設定。
それをもとにリハビリの計画を作成し、訓練のメニューに反映します。 この計画に基づき、専門職員と利用者がマンツーマンで進めるのが「個別リハビリ」です。 また、他の利用者とともに行う体操やトレーニングなどの「集団リハビリ」も実施します。 |
| 健康状態のチェック | 負担なくリハビリを進めるため、看護師が中心となって体調や健康状態の確認をします。 |
| 日常生活のサポート | 必要な人は、食事や入浴、排せつなどの介助を受けることも可能。
また、自宅からの送迎は施設のドライバーや介護職員が担当してくれます。 |
| レクリエーション | 他の利用者と一緒に脳トレゲームをしたり、工作などの趣味活動を楽しんだりする時間も充実。
他者と交流する機会を持つことで、QOLの向上にも期待できます。 |
デイケアは、デイサービスと比べて医療やリハビリを強化しているので、たとえば胃ろうや痰吸引などの医療的ケアが必要な方や、集中的にリハビリを希望する方が多く利用されています。
デイケアの利用条件
デイケアを利用するためには、「要介護・要支援認定を受けること」「医師からリハビリが必要だと診断されること」の2点を満たす必要があります。
要介護・要支援認定を受ける
デイケアは要介護1~5の全ての人が利用できます。
要支援1、2の認定を受けた人は、要介護状態になるのを防ぐための「介護予防通所リハビリテーション」が利用可能です。
日常生活上の支援に加え、「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」に関するサービスを選択できます。
医師からリハビリが必要だと診断を受ける
適切なリハビリを実施するため、デイケアに申し込む際には、医師が作成した「診療情報提供書」や「健康診断書」の提出が必須です。
かかりつけの医師がいない場合は、市区町村が指定する医師の診断を受けましょう。
デイケアにかかる費用
介護サービスを検討する上で費用面は気になるポイントです。デイケアにはどれくらいの費用が必要なのか、詳しく見てみましょう。
利用時の費用の内訳
デイケアの利用料金は、大まかに分けると「基本料金」+「サービス加算」+「その他の費用」の3つで構成されます。
基本料金
【要支援の場合】
要支援者のデイケアは、基本料金が月額制なのが特徴です。
日常生活に必要な支援をする共通的サービスに加え、下表のような選択的サービスの組み合わせによって料金が決まります。
1か月あたりの基本料金は以下の表の通りです。
| 共通的サービス/選択的サービス | 項目 | 費用 |
|---|---|---|
| 共通的サービス | 要支援1 | 2,268円 |
| 要支援2 | 4,228円 | |
| 選択的サービス | 運動器機能向上 | 225円 |
| 栄養改善 | 200円 | |
| 口腔機能向上(Ⅰ) | 150円 | |
| 口腔機能向上(Ⅱ) | 160円 |
※自己負担1割の場合
※参考:厚労省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
※参考:厚労省ホームページ「どんなサービスがあるの? – 通所リハビリテーション(デイケア)」
【要介護の場合】
要介護者の基本料金は、要介護度や利用時間、事業所の規模によって異なります。
金額は1回の利用ごとに算定する仕組みです。
例として、通常規模の事業所の基本料金を以下の表にまとめました。
通常規模とは、前年度の1か月あたりの利用者数が750人以内の事業所のことです。
| 要介護度 | 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 366円 | 380円 | 483円 | 549円 | 618円 | 710円 | 762円 |
| 要介護2 | 395円 | 436円 | 561円 | 637円 | 733円 | 844円 | 903円 |
| 要介護3 | 426円 | 494円 | 638円 | 725円 | 846円 | 974円 | 1,046円 |
| 要介護4 | 455円 | 551円 | 738円 | 838円 | 980円 | 1,129円 | 1,215円 |
| 要介護5 | 487円 | 608円 | 836円 | 950円 | 1,112円 | 1,281円 | 1,379円 |
※1単位=10円、自己負担1割の場合
※参考:厚労省資料「介護報酬の算定構造」
※参考:厚労省資料「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
サービス加算
基本料金に加え、別途で加算されるサービスもあります。例えば、「リハビリテーションマネジメント」や「入浴介助」、「栄養改善」などが加算対象です。
例)
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 6月以内 → 560円/月
- 入浴介助加算(Ⅰ) → 40円/回
- 栄養改善加算 → 200円/回(月に2回まで)
その他の費用
基本料金とサービス加算の他、食費やおやつ代、オムツ代などもかかります。
月額費用の内訳
実際にデイケアを利用した場合、どれくらいの料金がかかるのでしょうか。
以下の例をもとに、1か月あたりの費用の目安を試算してみましょう。
【1か月あたりの費用の目安例】
- 要介護度1で自己負担割合は1割
- 通常規模の事業所
- 1回あたり6時間で月8回の利用
- 入浴介助加算(Ⅰ)を利用
- 1回あたりの食費やオムツ代などが合計800円
710円(基本料金)+40円(入浴介助加算)=750円(介護保険の適用分)
750円+800円(食費など)=1,550円(1回あたりの自己負担額)
1,550円/回×月8回=12,400円(1か月あたりの自己負担額)
自己負担額
デイケアは介護保険が適用されるため、料金の全額を自己負担する必要はありません。自己負担の割合は原則として1割です。
ただし、一定以上の所得がある場合は、自己負担が2~3割になるので注意してください。
例えば、要介護1の人が通常規模の事業所を1回で6時間利用した場合、本来の1回あたりの基本料金は7,100円です。
この基本料金には介護保険が適用されるため、利用者が自己負担する額は7,100円×10%の710円で済みます。
デイケアの基本料金とサービス加算は介護保険が適用されますが、食費やオムツ代などは全額自己負担です。
食費などは施設によって金額が違うため、見学などの際に確認することをおすすめします。
デイケアのメリットは?
続いて、デイケアを利用するメリットを紹介します。
【デイケアのメリット】
- 専門的なリハビリや医療ケアが受けられる
- 他者と交流する機会が増える
- 家族の介護負担を減らせる
メリット①専門的なリハビリや医療ケアが受けられる
専門の資格を持った職員によるリハビリや医療ケアに力を入れている点は、デイケアの大きなメリットです。
利用者それぞれの状態に合わせた計画を作成し、リハビリを進めていきます。
また、機器や設備が充実した環境で訓練できるのも魅力です。
メリット②他者と交流する機会が増える
身体機能が衰えると、自宅にこもりがちになってしまうのが心配な点です。
デイケアでは集団リハビリやレクリエーションなど、他の利用者や職員と交流できる時間も設けられています。
デイケアに通って社会とのつながりを保つことで、精神的にも良い影響が期待できます。
メリット③家族の介護負担を減らせる
デイケアではリハビリだけでなく、食事や入浴、排せつなど日常生活のサポートも必要に応じて提供します。
デイケアを利用している間、同居する家族は気分転換ができるなど、介護負担の軽減につながるでしょう。
デイケアのデメリットは?
一方で、デイケアにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
【デイケアのデメリット】
- 自宅とは異なる環境でのリハビリになる
- 施設によって設備に差がある
- リハビリは完全にマンツーマンではない
デメリット①自宅とは異なる環境でのリハビリになる
デイケアは施設に通ってリハビリを進めるため、住み慣れた自宅の手すりや階段、浴槽などを使った訓練はできません。
例えば「自宅のベッドでの昇降が難しい」「自宅の浴槽をまたぐ練習がしたい」など、自宅での生活環境に具体的な悩みがある方も多いでしょう。
そのような場合、施設内での訓練だけでは不十分に感じる可能性もあります
デメリット②施設によって設備に差がある
デイケアは施設によって規模もサービス内容もさまざまです。
どの施設でも同じ設備や機器がそろっているとは限りません。
見学や体験利用の際には、必要とする設備やサービスが用意されているかどうか、しっかりとチェックすることをおすすめします。
デメリット③リハビリは完全にマンツーマンではない
デイケアでは他の利用者のリハビリも並行して進めるため、常にマンツーマンで個別リハビリを受けられるわけではありません。
そのため、利用者一人ひとりへの対応には限度があるといえます。
他の介護サービスとの違い
介護サービスにはデイケア以外にも、デイサービスや訪問介護、訪問リハビリなどが存在します。デイケアとはどのような違いがあるのでしょうか。
それぞれのサービスの特徴を、以下の表にまとめました。
| デイケア | デイサービス | 訪問介護 | 訪問リハビリ | |
|---|---|---|---|---|
| サービス内容 | 施設でのリハビリや生活支援、
レクリエーションなど |
食事や入浴、レクリエーション、
介護職員による機能訓練など |
食事や入浴、排せつなどの身体介護や、
掃除や洗濯、買い物などの生活援助 |
専門職が自宅を訪問し、
リハビリを実施 |
| 主な利用目的 | 心身機能の維持・回復のためのリハビリ | 利用者の孤立感の解消、
心身機能の維持・向上、 家族の介護負担の軽減 |
利用者ができる限り
自宅で自立した生活を送るためのサポート |
心身機能の維持・回復のための
リハビリ |
| 対象者 | 自宅で暮らす要介護・要支援認定を受けた人で、
リハビリが必要な人 |
自宅で暮らす要介護認定を受けた人 | 自宅で暮らす要介護・要支援認定を受けた人 | 自宅で暮らす要介護・要支援認定を受けた人で、
リハビリが必要な人 |
| 費用 | デイサービスに比べると2~3割程度高い | 1回あたり1,000~2,000円が相場 | 20分未満の身体介護は163円/回
20~45分の生活援助は179円/回など(自己負担1割の場合) |
1回(20分)あたり308円(自己負担1割の場合) |
| 要介護度 | 要介護1~5
要支援1、2 (要支援者は介護予防通所リハビリテーション) |
要介護1~5 | 要介護1~5
要支援1、2 (要支援者は介護予防訪問介護) |
要介護1~5
要支援1、2 (要支援者は介護予防訪問リハビリテーション) |
| スタッフ | 医師の配置が必須。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の他、 看護師や介護職員が在籍 |
生活相談員
看護職員 介護職員 機能訓練指導員 |
介護福祉士などの
資格を持ったホームヘルパー |
医師の配置が必須。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が在籍 |
デイサービスとの違い
デイケアと混同されがちなのがデイサービス。
在宅の要介護者が施設に通ってサービスを受ける点は共通ですが、利用目的などに違いがあります。
リハビリや医療ケアが手厚いデイケアに対し、デイサービスは日常生活上の支援をメインとしています。
そのため、医師やリハビリの専門職の配置は必須ではなく、費用もデイケアに比べると安めです。

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
訪問介護との違い
訪問介護はホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、住み慣れた自宅で自立した日常生活を送れるように、身体介護や生活援助を行います。
買い物の代行や食事準備、着替えの補助など幅広いサービス内容がありますが、専門資格が必要なリハビリや医療ケアには対応していません。

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問リハビリとの違い
訪問リハビリも、デイケアと同様にリハビリに特化したサービスです。
デイケアとの大きな違いは、リハビリを実施する場所。施設に通うデイケアとは違い、訪問リハビリでは作業療法士などの専門職が利用者の自宅を訪問します。
自宅でのリハビリのため、より日常生活に沿った訓練ができるのがメリットです。
一方、他の利用者との交流などはできません。

訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
デイケアを選ぶ時のポイント
無理なくリハビリを続けるためにも、利用者本人に合ったデイケアを見つけることは重要です。
施設選びでは、どのようなポイントに注意すればいいのでしょうか。
【デイケアを選ぶポイント】
- 必要なリハビリを受けられるか
- 目的に合ったサービスが整っているか
- サービスの提供時間などが希望に合っているか
- 施設の雰囲気が好みに合うか
ポイント①必要なリハビリを受けられるか
利用者一人ひとりの状態によって、リハビリに必要な設備は異なります。
また、デイケアには理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などの専門職が勤務していますが、全ての職種が在籍しているとは限りません。
必要なリハビリを受けられる環境かどうか、事前にしっかりと確認しましょう。
ポイント②目的に合ったサービスが整っているか
デイケアでは必要に応じ、食事や入浴、排せつなどの介助も受けられます。
対応できる範囲は施設によるため、利用者の状態に合った生活支援が受けられるかチェックしましょう。
例)
- 寝たきりの状態でも入浴介助は可能か?
- 車いすの送迎に対応しているか?
ポイント③サービスの提供時間などが希望に合っているか
デイケアの事業者によっては、サービスの提供時間が1~2時間などの短時間に限られることもあります。
利用者本人の体力面や家族の負担などを考慮し、適切な時間で利用できるデイケアを選ぶようにしましょう。
ポイント④施設の雰囲気が好みに合うか
デイケアによって、職員や他の利用者の雰囲気はさまざま。
施設になじめないと、通うのが嫌になってリハビリを続けるのが困難になる恐れもあります。
可能な限り利用者本人とともに見学に行き、居心地は良さそうか、職員は親身に対応してくれるかなどを確認するのがおすすめです。
デイケアを利用するまでの流れ
デイケアを利用するためには、どのような手続きや準備が必要なのでしょうか。大まかな流れをご説明します。
【STEP.1】要介護・要支援認定の申請
要介護・要支援認定を受けていない場合は、まず市区町村への申請手続きが必要です。
申請には介護保険被保険者証が必要なため、忘れずに用意してください。
申請後は市区町村の職員による訪問調査などを経て、1か月以内に結果が通知されます。
【STEP.2】ケアマネジャーに相談~施設の見学
担当のケアマネジャーにデイケアを利用したい旨を相談します。
そして、リハビリの内容や利用者の希望条件に合う施設の候補をピックアップ。
候補が決まったら実際に見学や体験利用をし、通いたい施設を決めます。
【STEP.3】医師に書類の作成を依頼
施設が決まったら、かかりつけの医師に診療情報提供書や健康診断書の作成を依頼します。
作成には1~2週間ほどかかるため、スケジュールに余裕を持って依頼するようにしましょう。
【STEP.4】申し込み~面談
必要な書類を提出したら、デイケアの職員と面談を実施。
デイケア側は書類と面談の内容を踏まえて会議を開き、受け入れが可能かどうかを判定します。
【STEP.5】ケアプランの作成
施設の利用が決定したら、ケアマネジャー(要支援認定の場合は地域包括支援センター)に「ケアプラン」を作成してもらいます。
ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ・どれだけ利用するかを決めた計画です。
【STEP.6】契約して利用を開始
ケアプランに問題が無ければ施設と正式に契約。指定された日から利用をスタートします。
ビジネスパーソンのみなさまへ
本記事ではデイケアについて説明してきました。そのポイントをおさらいします。
【デイケアのポイントおさらい】
- デイケアはリハビリや医療ケアに特化した介護保険サービス
- 国家資格を持った職員がいる施設に通い、専門的なリハビリが受けられる
- 要介護・要支援認定を受け、医師からリハビリが必要と診断されるのが利用条件
- 家族の介護負担を軽減できるメリットもある
例えば高齢者が病気やケガで入院した場合、退院後もリハビリが必要となるケースは珍しくありません。
デイケアは、そのような高齢者本人にとってはもちろん、介護をする家族にとっても強い味方になるでしょう。
デイケアの利用を検討する際は、ケアマネジャーなどに相談するのもおすすめです。
利用者に合ったデイケアを選び、上手に活用していきましょう。