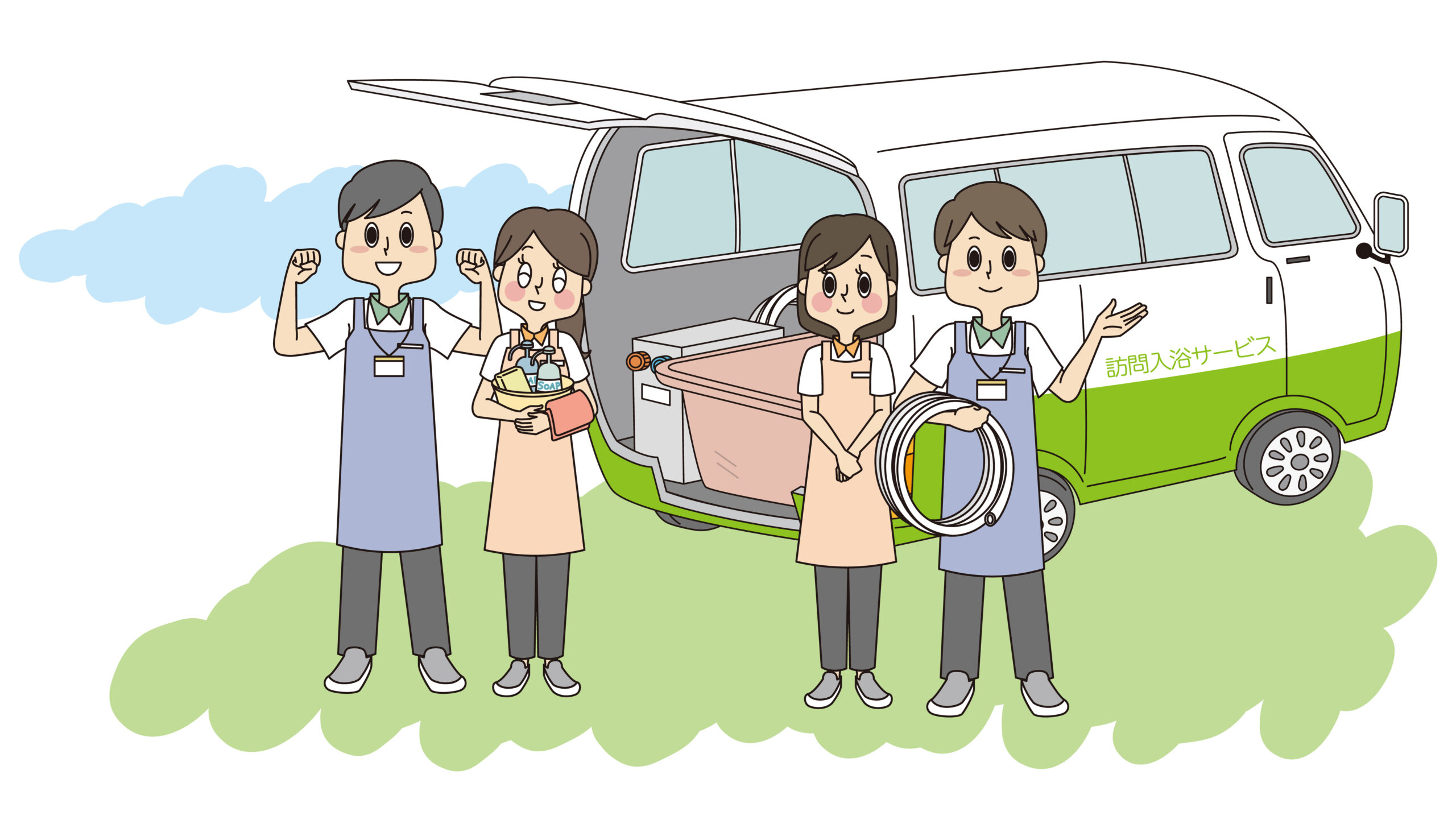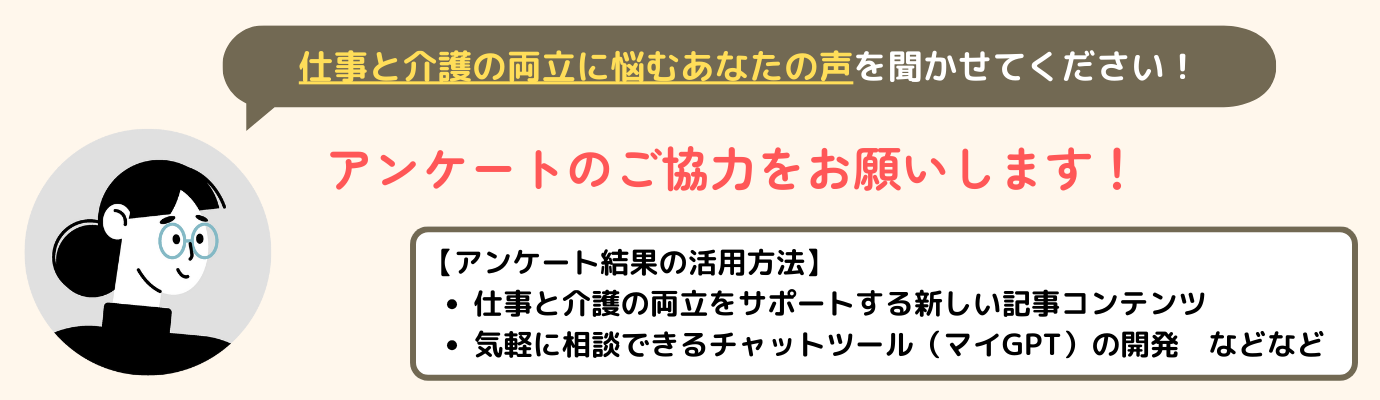「自力での入浴が難しい」「家族のサポートだけではお風呂に入れない」とお困りの方はいませんか?
そんな方におすすめなのが、『訪問入浴介護』。
訪問入浴介護とは、看護師と介護職員が利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽を使って入浴の介護を行うサービスです。
今回の記事では、訪問入浴介護のサービス内容や利用条件、費用などについて詳しく解説します。
居宅介護を検討している方、介護負担を減らしたいとお考えのビジネスパーソンのみなさま方は是非参考にしてください。
目次
訪問入浴介護とは?
訪問入浴介護とは、寝たきりの方や足腰の機能が衰えている方など、浴室への移動を含めて自力で安全に入浴できない方専用のサービスです。
健康状態や希望に応じて、全身浴や部分浴、清拭を行い、身体の清潔や心身のリフレッシュなどを促します。
持参された専用の簡易浴槽を使って入浴するため、「自宅の浴室が狭い」「ベッドから浴室までの移動が大変」など、入浴環境が整っていない場合も利用できる点が魅力です。
入浴時の洗髪や洗体だけでなく、入浴前後の健康チェック、浴槽の準備や片付けもお任せできます。
ケガのリスクや介護負担の大きい入浴をお手伝いしていただくことで、居宅での生活を望む要介護者と親の介護をみているビジネスパーソンのみなさま双方を支えています。
介護保険法での定義
介護保険法における訪問入浴介護の定義は、『居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護』とされています。
居宅における入浴の援助を行うことで、利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持、介護負担の軽減を図り、在宅介護を支援するサービスです。
訪問入浴介護は、デイサービスやショートステイなどの居宅介護サービスと同様に、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って提供されます。
そのため、訪問入浴介護の利用を希望する場合、まずは担当のケアマネジャーへの相談が必要です。
担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターや市町村の介護相談窓口に相談しましょう。

介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
介護は誰もが直面するシビアな課題ですが、重責を担っている40~50歳のビジネスケアラーの皆さんにとっては、仕事と介護の両立はご自身の生活に大きな影響を与えかねません。 そんな介護に悩むビジネスケアラーの助けとなる「地域包括支援センター」について解説します。地域包括支援センターの設置背景や役割を...
そして、数ある事業所の中から、利用者に合うものを選定し、同意書や契約書を交わした上でサービスの提供が開始されます。
利用者の状態が安定していると主治医が判断した場合、介護職員3名でサービスの提供ができますが、看護職員1名と介護職員2名での対応が一般的です。
訪問入浴介護で提供するサービスは、入浴に不随する行為に限定されており、看護師が同行しても痰の吸引や摘便などの医療行為はできません。
医療行為が必要な方は、訪問看護などの併用が必要です。
※参考:介護保険法|e-Gov法令検索
訪問入浴介護のサービス内容
訪問入浴介護とは、利用者の居宅を訪問入浴車で訪問し、持参した浴槽を使って、入浴の介護を行うサービスです。
平均的な所要時間は、準備や片付けも含めて50分前後になります。
つぎに、訪問入浴介護のサービス内容について紹介します。
【訪問入浴介護のサービス内容】
- 入浴前後の健康チェック(体温・血圧・脈拍・呼吸などの確認)
- 浴槽とお湯の準備・片付け
- 衣服の着脱
- ベッド~浴槽の移乗
- 入浴(全身浴・部分浴・清拭)
上記のサービスを基本とし、爪切りや髭剃りなどのケア、マイクロバブルや温泉水の使用といった特色をもつ事業所もあります。
訪問入浴介護の利用条件
訪問入浴介護の利用条件について説明します。
【訪問入浴介護の利用条件】
- 要介護1~5の介護認定を受けた方
(主治医から入浴の許可を得ている方) - 要支援1~2の方
(「自宅に浴室がない」などの条件付きの方)
要介護1〜5と認定を受けた方については、健康状態に問題がなく、かつかかりつけ医から入浴を許可されている方のみが訪問入浴介護をご利用できます。
なお、要支援1〜2の方は、介護予防サービスである「介護予防訪問入浴介護」を利用することができます。
訪問入浴介護にかかる費用
訪問入浴介護は、「要介護」「要支援(介護予防訪問入浴介護)」や、全身浴・部分浴・清拭など、サービス内容によって費用が変わります。
事業所によっても変動するため、利用にかかる費用を事前に確認しておきましょう。
月額費用の内訳
介護保険は、要介護認定の区分ごとに支給限度額が設定されています。
要介護認定を受けたからといって、際限なく介護サービスを利用できるわけではありません。
介護保険の支給限度内での利用を希望する場合、介護度や併用しているサービスなどによって、ひと月に利用できる回数が異なります。
基本サービス費の1,266円に、サービス内容や事業所の提供体制に応じて加算・減算したものが1回の費用です。
利用回数によって月額の費用が算出されます。
自己負担額
訪問入浴介護の自己負担額は、原則1割とされています。
一定以上の所得がある方は、2割または3割負担となるため、要介護認定を受けた際に交付された『介護保険負担割合証』を確認しましょう。
介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用した場合、全額自己負担となります。
つぎに、1割負担の方の基本的な自己負担額を紹介します。
| 人員 | サービス内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 看護職員1名と介護職員2名 | 全身浴 | 1,266円 |
| 部分浴・清拭 | 1,139円 | |
| 介護職員3名 | 全身浴 | 1,202円 |
事業所や地域によって、自己負担額は前後します。費用の詳細は、事前に確認しておきましょう。
訪問入浴介護のメリットは?
訪問入浴介護は、在宅介護を支える大切な介護サービスの1つです。
ここでは、訪問入浴介護について、具体的なメリットを紹介します。
【訪問入浴介護のメリット】
- 健康維持・改善に繋がる
- QOL(生活の質)が向上する
- 費用負担を抑えられる
- 大幅な住宅改修の必要がない
- 介護負担の軽減に繋がる
メリット①健康維持・改善に繋がる
身体の清潔を保つ入浴は、皮膚の感染症や褥瘡(床ずれ)の予防に効果的です。
裸になって直接皮膚の状態を確認できるため、状態の変化に気付きやすいという利点もあります。
さらに、温かい湯船に入って身体が温まると、血行や新陳代謝が促進されるため、訪問入浴介護の利用は健康維持や改善に繋がります。
メリット➁QOL(生活の質)が向上する
入浴は、身体を清潔に保つだけでなく、心身のリラックスにも効果的です。
副交感神経の働きを高めて身体や心の強張りをやわらげ、深い睡眠も促します。
また、家族以外とコミュニケーションをとることで気分転換にもなるため、訪問入浴介護はQOLの向上に繋がります。
メ
リット➂費用負担を抑えられる
介護保険が適用される訪問入浴介護は、1割の自己負担額で利用できます。
所得額によって、2割もしくは3割負担になる場合もありますが、費用負担を抑えて利用できる点が大きなメリットです。
継続的な利用を望む方々にとって、予算を超えない範囲で利用できるかは大切な条件と言えるでしょう。
メリット④大幅な住宅改修の必要がない
訪問入浴介護は、利用者の居宅に持参した浴槽を使用し、入浴の介護が行われます。
そのため、浴室や脱衣場、寝室から浴室へ移動する経路など、入浴のための大幅な改修が必要ありません。
賃貸で住宅改修が難しかったり、改修にかかる金銭的負担が大きかったりといった場合も、安心して利用できます。
メリット⑤介護負担の軽減に繋がる
在宅介護において、入浴は介護負担が非常に大きいものです。
転倒やケガへの配慮、介護者の体調管理、ベッドから浴槽への移乗など、介護者には身体的・精神的に大きな負担がかかります。
訪問入浴介護の利用は、介護を担うご家族は休息となり、介護負担軽減に繋がります。
訪問入浴介護のデメリットは?
訪問入浴介護は、在宅生活を続ける要介護者と介護者の双方を支える重要なサービスですが、メリットばかりではありません。
ここでは、訪問入浴介護について、具体的なデメリットを紹介します。
【訪問入浴介護のデメリット】
- ストレスになる場合もある
- 医療行為はできない
- 訪問介護に比べて費用が高い
- 駐車スペースを用意する必要がある
デメリット①ストレスになる場合もある
利用者によっては、家族以外に裸を見られることや異性に介護をされること、他人が自宅に来ることなどに抵抗を感じる方もいます。
事前の説明をしっかりと行い、同性のスタッフに対応をお願いできるかなども確認しておきましょう。
デメリット➁医療行為はできない
訪問入浴介護で提供できるサービスは、入浴に関する行為に限定されています。
看護師が同行しても、痰の吸引や摘便、褥瘡(床ずれ)のケアなどの医療行為には対応できません。
医療行為が必要な場合は、訪問看護などのサービスを検討する必要があります。
デメリット➂訪問介護に比べて費用が高い
訪問入浴介護と同様に、居宅での入浴を支援するサービスが訪問介護です。
訪問介護では、基本的に1名のスタッフが利用者の居宅を訪問し、利用者宅の浴室を使用して入浴の介助を行います。
必要な人員や備品、設備に違いがあるため、訪問介護に比べて訪問入浴介護の方が、費用は高くなります。
デメリット④駐車スペースを用意する必要がある
訪問入浴介護は、3名のスタッフと共に、入浴の設備や備品を持参するため、訪問入浴車を使用します。
そのため、訪問入浴介護を利用する際には、駐車スペースを確保しておかなければなりません。
駐車スペースがない場合、サービスを利用できない可能性もあります。
他の介護サービスとの違い
訪問入浴介護は、専用の浴槽を利用者の居宅に持参し、入浴の介護を3名体制で行うサービスです。
介護保険で利用できる介護サービスには、訪問入浴介護以外にもさまざまな種類があります。
ここでは、訪問入浴介護と他介護サービスとの違いについて説明します。
訪問介護との違い
訪問介護とは、介護福祉士やホームヘルパーが利用者の居宅を訪問し、日常生活上のサポートを行うサービスです。
食事や排せつ、入浴などの「身体介護」、掃除や洗濯、調理、買いものなどの「生活援助」、「通院時の乗車・降車などの介助」といったサービスを提供します。
| 比較項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 身体介護、生活援助、通院時の乗車・降車などの介助 |
| 利用目的 | 日常生活のサポート |
| 利用対象者 | 要介護1~5の認定を受けている方 |
| 費用の目安 (1割負担の場合) |
200〜500円/回 (利用時間やサービス内容などによって異なる) |
| スタッフ | 介護福祉士やホームヘルパー |

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問看護との違い
訪問看護とは、主治医の指示に基づいて保健師や看護師、理学療法士などが利用者の居宅を訪問し、専門的なケアを行うサービスです。
褥瘡の処理や点滴・注射、リハビリテーション、ターミナルケア、家族への介護指導・相談などのサービスを提供します。
| 比較項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 病状確認や点滴、医療機器の管理、褥瘡の処理などの専門的なケア |
| 利用目的 | 在宅療養生活の維持・安定 |
| 利用対象者 |
|
| 費用の目安 (1割負担の場合) |
500〜1,000円/回 (事業所の種別、スタッフの職種、利用時間などによって異なる) |
| スタッフ | 看護師、保健師、理学療法士など |

高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
訪問リハビリテーションとの違い
訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、日常生活の自立や社会参加を促すサービスです。
寝返りや歩行などの「機能訓練」、着替えや排せつ、入浴などの「生活動作訓練」、「住宅改修のアドバイス」、「介助方法の指導」などを行います。
実際の生活に即したリハビリテーションを行うことで、動作の自立や介助量の軽減に繋がる点が特徴です。
| 比較項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 機能・生活動作訓練、福祉用具・住宅改修のアドバイスなど |
| 利用目的 | 日常生活動作の自立、社会参加の促進 |
| 利用対象者 | 要介護度1〜5の認定を受け、主治医の許可を得た方 |
| 費用の目安 (1割負担の場合) |
300〜500円/回 (利用時間やサービスの内容によって異なる) |
| スタッフ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |

訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
デイサービスとの違い
デイサービスとは、利用者がデイサービスセンターなどに通い、機能訓練や日常生活の援助を受けるサービスです。
利用者の居宅と施設間の送迎をはじめ、日帰りで食事や入浴、機能訓練、趣味活動などが提供されます。
| 比較項目 | 概要 |
|---|---|
| サービス内容 | 食事や排せる、入浴、機能訓練、趣味活動、自宅と施設間の送迎など |
| 利用目的 | 日常生活のサポート、介護負担の軽減 |
| 利用対象者 | 要介護度1〜5の認定を受けている方 |
| 費用の目安 (1割負担の場合) |
1,000〜2,000円/回 (施設の規模や利用時間によって異なる) |
| スタッフ | 看護職員、介護職員、機能訓練指導員など |

ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
ビジネスパーソンの皆さまが、「いざ親の介護をしなければ」と意気込んだものの、家族だけでは対応しきれないことも出てくるものです。 そんなとき、みなさまの介護をサポートしてくれるサービスのひとつが、今回ご紹介する「デイサービス(通所介護)」です。 それではデイサービス(通所介護)の具体的なサ...
訪問入浴介護を選ぶときのポイント
訪問入浴介護は、事業所によって費用・サービス内容の詳細が異なります。
ここでは、「どの事業所を選べばいいかわからない」という方へ向け、訪問入浴介護の選び方や注意点について、紹介します。
【訪問入浴介護を選ぶときのポイント】
- サービス内容の詳細について
- 衛生管理・安全面の配慮について
- キャンセル時の料金や対応について
- 緊急時の対応について
ポイント①サービス内容の詳細について
訪問入浴介護は、入浴に特化した介護サービスです。
提供できるサービスは、入浴に付随した行為と定められているものの、事業所によってサービス内容が異なります。
例えば、爪切りや髭剃り、保湿ケアなどに対応していたり、温泉水や高濃度炭酸泉を取り入れていたりと特色のある事業所は少なくありません。
特に、同性スタッフによる対応の可否が大きな決め手になる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
ポイント②衛生管理・安全面の配慮について
訪問入浴介護では、感染症への抵抗力が低く、重症化リスクの高い高齢者、および障がい者などの素肌に触れ、入浴のサポートを行います。
スタッフの手洗いや消毒はもちろん、備品や機材が安全に配慮されたもの、なおかつ適切に清掃・消毒されていることが非常に重要です。
命に関わる場合もあるため、事業所の衛生対策や安全管理体制を確認した上で、利用する事業所を選定しましょう。
ポイント③キャンセル時の料金や対応について
訪問入浴介護の利用をキャンセルすると、利用料の一部もしくは全額にあたるキャンセル料が発生する場合があります。
体調不良や入院などのやむを得ない事情でのキャンセルは、キャンセル料を不要としている事業所が一般的です。
事業所によってキャンセル時の規定や振り替え日時の提案などの対応が異なるため、事前に確認しておきましょう。
ポイント④緊急時の対応について
訪問入浴介護の運営基準として、緊急時は主治医や協力医療機関へ速やかに連絡を行い、必要な措置を講じなければならないと定められています。
体調変化や自然災害など、緊急時にスタッフが迅速で適切な対応ができるかを確認しましょう。
主治医や協力医療機関との連絡体制、救急車を要請するか否かなど、具体的な対応策の提示があると、万が一の際にも安心してお任せできます。
訪問入浴介護を利用するまでの流れ
訪問入浴介護を利用するためには、必要な手順・手続きが必要です。
つぎに、訪問入浴介護を利用するまでの具体的な流れについて説明します。
【訪問入浴介護を利用するまでの流れ】
- 【STEP.1】要介護認定を申請する
- 【STEP.2】要介護1~5の認定を受ける
- 【STEP.3】ケアプランを作成する
- 【STEP.4】事業所と契約を結ぶ
- 【STEP.5】利用を開始する
【STEP.1】要介護認定を申請する
介護保険サービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
市区町村の窓口に介護保険被保険者証などを持参し、手続きを行いましょう。
申請を受けた市区町村は、申請者の居宅や施設へ調査員を派遣し、普段の様子や心身の状態を確認します。
【STEP.2】要介護1~5の認定を受ける
調査書や主治医の意見書を基に、要介護の区分が判定されます。
要支援から要介護まで7つの区分があり、区分ごとに利用できるサービス内容や利用上限額が異なる点が特徴です。
認定結果は、申請日から30日以内に認定結果が通知されます。
【STEP.3】ケアプランを作成する
利用者と家族の希望・相談をヒアリングしながら、担当のケアマネジャーがケアプランを作成します。
ケアプランに沿って、介護サービスが提供されるため、訪問入浴介護の利用や回数の希望を伝えましょう。
【STEP.4】事業所と契約を結ぶ
市区町村に用意されている事業所のリストを活用したり、ケアマネジャーのアドバイスを受けたりしながら、利用する事業所を選びましょう。
気になる事業所から説明を受け、利用を決めた後に契約書や同意書を交わします。
【STEP.5】利用を開始する
ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って、訪問入浴介護の利用を開始します。
日時の変更や利用回数の増減などを希望する際は、事業所やケアマネジャーに相談しましょう。
要介護認定には有効期限がありますが、時期がきたら更新の申請をすることで、引き続きサービスを利用できます。
ビジネスパーソンのみなさまへ
今回は、訪問入浴介護について、サービスの内容や利用条件、費用、他介護サービスとの違いなどについて説明しました。
【訪問入浴介護のまとめ】
- 看護職員1名と介護職員2名、もしくは介護職員3名で入浴の介護を行う
- 居宅の浴室を使用せず、持参した浴槽を使用する
- 要介護1~5の認定を受け、主治医の許可を得ている方がサービスを利用できる
- 介護負担の軽減に繋がる
- 医療行為はできない
- 訪問介護に比べて費用が高い
- 駐車スペースを用意する必要がある
訪問入浴介護は、居宅介護を支える重要なサービスの1つです。
利用者の健康維持や向上だけでなく、介護負担の軽減を図り、利用者とご家族の双方をサポートします。
「両親と同居しているが、自宅での入浴が難しくなってきた」「仕事と介護の両立をしたい」といった方におすすめの介護サービスです。