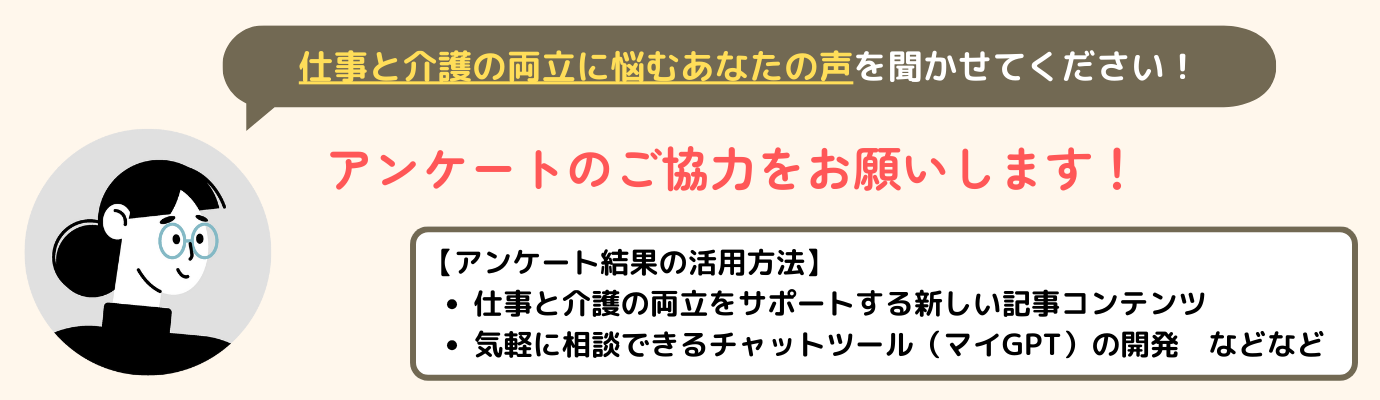「要介護になった親を自宅で介護することになった」「離れて暮らす要介護の親が心配」
そんな時に役立つのが、医療の専門職が自宅を訪問して健康管理指導を行う「居宅療養管理指導」です。
安心してサービスを受けられるよう、利用条件や費用、メリット・デメリット、事業者を選ぶ際のポイントなどを解説します。
目次
居宅療養管理指導とは?
「居宅療養管理指導」とは、環境や身体的要因により通院することが困難な人を対象に、医療の専門職である医師や歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問して健康管理指導を行うサービスです。
自宅での療養・介護において「食事のメニューや調理法、栄養管理はどうすればいい?」
「薬を正しく飲むためには?」「歯はきちんと磨けているか?虫歯の予防は?」など不安はつきものです。
そんな不安に対し「居宅療養管理指導」では、主治医の指示に基づく栄養バランスを考えた食事の指導や薬の正しい服用方法、歯・口腔内のケアなど、健康管理に関するアドバイスを受けることができます。
居宅療養管理指導を受けられるのは、要介護1~5に認定されている65歳以上の高齢者です。要支援1~2を受けている人は、介護予防居宅療養管理指導が適用されます。
訪問によるサービスのため、通院にかかる身体的負担も軽減することが期待できます。
居宅療養管理指導のサービス内容
ここでは居宅療養管理指導として、医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士から受けることができるサービスと月々に利用できる回数について紹介します。
| 医師・歯科医師 | |
|---|---|
| 訪問回数 |
|
| サービス内容 |
|
| 薬剤師 | |
|---|---|
| 訪問回数 |
|
| サービス内容 |
|
| 管理栄養士 | |
|---|---|
| 訪問回数 |
|
| サービス内容 |
|
| 歯科衛生士 | |
|---|---|
| 訪問回数 |
|
| サービス内容 |
|
居宅療養管理指導のサービス利用までの流れ
| サービス利用の流れ | |
|---|---|
| STEP.1 | 担当のケアマネジャーに利用者の身体的・精神的状態について相談しましょう。 |
| STEP.2 | ケアマネジャーから居宅療養管理指導を利用すべきか判断してもらいましょう。 |
| STEP.3 | 居宅療養管理指導を利用した方が良いと判断された場合は、ケアマネージャーから担当医師へ連絡してもらいます。 |
| STEP.4 | ケアマネジャーがあなたに合ったケアプランを作成します。 |
| STEP.5 | 居宅療養管理指導のサービスを必要なタイミングで開始することになります。 |
居宅療養管理指導の利用条件
| 居宅療養管理指導の対象者 |
|---|
| 要介護1以上の高齢者(65歳以上)
または 特定疾病(※)により要介護1以上の認定を受けた40歳~64歳までの方 |
要介護1以上の高齢者(65歳以上)または特定疾病(※)により要介護1以上の認定を受けた40歳~64歳までの方が対象となり、居宅療養管理指導のサービスを利用することができます。
※特定疾病とは、がん・関節リウマチ・パーキンソン病など加齢に伴って生ずる心身の障害に指定されている16の疾患です。
介護保険制度は65歳以上が原則対象ですが、特定疾病の場合は40歳からサービスを利用することができます。
居宅療養管理指導にかかる費用
介護保険の点数による費用の1割~3割負担となっています。
厚生労働省が発表している「介護報酬の算定構造(令和6年4月)」によると、医師による往診の金額は、1回あたり平均約500円です。
※訪問先・改定などで点数が変わるため、その都度確認しましょう。
利用時の費用の内訳・月額費用の内訳・自己負担額
《利用料金の目安》
介護保険1割負担・訪問1回あたりの費用(自己負担額)をご紹介します。
※参考サイト:厚生労働省 老健局「居宅療養管理指導」より
※下記は介護保険1割負担の場合です。2割負担の場合は2倍、3割負担の場合は3倍の料金になります。
※末期の悪性腫瘍、中心静脈栄養を受けている利用者に対しては、薬局の薬剤師によるサービスを、2回/週、かつ、8回/月まで利用できます。
| 専門家 | 介護保険1割負担・訪問1回あたりの費用(自己負担額) |
|---|---|
| 医師 |
|
| 歯科医師 |
|
| 薬剤師 | 【医療機関の薬剤師】
【薬局の薬剤師】
|
| 管理栄養士 |
|
| 歯科衛生士 |
|
居宅療養管理指導のメリットは?
居宅療養管理指導は利用するメリットが多くあります。
自宅にいながら健康管理や指導を受けられるサービスならではのメリットです。それぞれご紹介していきましょう。
【居宅療養管理指導のメリット】
- メリット1:通院することなく、自宅で受けられる
- メリット2:要介護者の身体的負担を軽減できる
- メリット3:介護者にとっても身体的・時間の負担が軽減できる
- メリット4:日常生活で使うモノで指導してくれるのでわかりやすい!
- メリット5:アドバイスを家族みんなで共有できる
メリット1:通院することなく、自宅で受けられる
通院が困難な人も、居宅療養管理指導を利用することで、自宅にいながら薬の服用指導や栄養管理、虫歯の予防など、医療の専門職から直接指導を受けることができます。
メリット2:要介護者の身体的負担を軽減できる
介護を必要とする人にとって、電車や車での移動・歩行を必要とする通院は身体的に負担がかかるものです。
居宅療養管理指導は通院することなく、自宅に訪問して指導してくれるため、身体的に負担がありません。
メリット3:介護者にとっても身体的・時間の負担が軽減できる
仕事や子育てをしながらの通院介助は介護者にとっても大きな負担ですが、居宅療養管理指導の利用はビジネスケアラーにとっても時間的にも身体的にも負担を軽減につながります。
メリット4:日常生活で使うモノで指導してくれるのでわかりやすい!
自宅で指導を受けられるので、例えば正しい歯磨きの仕方や義歯の手入れなど、日頃使っている器具での指導や、調理環境をふまえた食事づくりの注意点・調理方法を指導してもらえます。
メリット5:アドバイスを家族みんなで共有できる
介護に関する注意点なども住環境にあわせた指導を受けられます。
家族で介護をする場合など、みんなでアドバイスを聞いて状況を把握し、共有することができます。
居宅療養管理指導のデメリットは?
居宅療養管理指導にはメリットの他、デメリットも存在します。デメリットを理解した上でサービスの利用を検討すると良いでしょう。
【居宅療養管理指導のデメリット】
- デメリット1:医療行為は受けられない
- デメリット2:主治医・医師の指示がないと利用できない
- デメリット3:利用回数に制限がある
- デメリット4:事業者は自分で判断・決定する必要がある
デメリット1:医療行為は受けられない
居宅療養管理指導は、あくまで健康管理や指導といったサービスのため、診断や治療などの医療行為は受けることができません。
※医師が訪問する場合は「訪問診療」「往診」とのセットになります。
デメリット2:主治医・医師の指示がないと利用できない
薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士など医師以外の専門職から指導を受ける際は、医師・歯科医師の指示がないと利用できません。
例えば食事メニューなども、医師・主治医の指示のもと、管理栄養士が組み立て、指導します。
デメリット3:利用回数に制限がある
月の利用回数に制限があります。
医師・歯科医師なら月に2回まで、薬剤師なら月に4回までと制限がありますので、ケアマネージャーに相談しながら利用していきましょう。
デメリット4:事業者は自分で判断・決定する必要がある
ケアマネージャーが事業者を探し、紹介してくれますが、どの事業者にするかを決めるのは利用者自身です。
安全に安心してサービスを受けられるよう情報収集をしたり、事前の確認を行う必要があります。
他の介護サービスとの違い
介護に関する訪問サービスは多数あり、内容・利用条件などさまざまです。その違いを把握しておきましょう。
訪問看護との違い
訪問看護とは、看護師・理学療法士・作業療法士などが利用者宅を訪問し、医療ケアを提供するサービスです。
病気や障害を持つ方がご家庭で安心して療養生活を送れるよう、医師の指示による医療処置やターミナルケア、機能回復・訓練のためのリハビリテーションなどが行われます。(介護保険適用)

高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
高齢化が加速し、団塊の世代すべてが75歳以上となる2025年問題を目前にした日本では、親の介護の問題を抱えるビジネスパーソンが急増しています。 いわゆるビジネスケアラーと呼ばれる方々で、仕事をしながら家族介護を行う人たちで、その数は約300万人に達すると言われています。 介護のための介護...
訪問介護との違い
訪問介護とは、介護福祉士・介護職員初任者研修修了者の資格を持つホームヘルパーが
利用者宅を訪問し、身体介護や生活援助を行うサービスです。
食事介助・入浴介助・清拭・排せつ介助・歩行介助・体位変換や掃除・洗濯・食事の準備・移動介助・爪切りなど(医療行為ではないもの)の支援が受けられます。(介護保険適用)

訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問介護は、要支援・要介護の高齢者ご本人や家族の自立した生活を支援するサービスです。 利用者のご自宅にホームヘルパーが訪問して、食事や入浴などの『身体介護』や、調理や掃除などの『生活援助』を行います。 ここでは、訪問介護で受けられるサービス内容や、利用料金、メリットデメリットを解説します...
訪問リハビリとの違い
訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などが利用者宅を訪問し、リハビリテーションを行うものです。
心身機能の回復・維持や日常生活の自立を目指し、主治医が必要性を認めた場合に、各種の機能訓練が行われます。(介護保険適用)

訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
訪問リハビリ(訪問リハビリテーション)とは、主治医が必要と判断した要介護者の自宅に、理学療法士や作業療法士などの専門家が利用者の自宅に訪れてリハビリを行うことです。 病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合や、退院・退所後の日常生活に不安がある場合などに、「身体機能が衰えている親の介護...
訪問診察・往診との違い
訪問診察とは、通院が困難で、自宅や施設で療養する人を対象に、医師が計画的に訪問し、診療や医療行為を行うものです。
一方、往診は患者からの要請に対し、医師が訪問して診療や医療行為を行うものです。(共に、医療保険適用)
居宅療養管理指導を選ぶ時のポイント
サービス開始後もトラブルなく安心して利用できるよう、事業者を選ぶ際のポイントをご紹介します。
【居宅療養管理指導を選ぶ時のポイント】
- 契約時に隅々まで内容を確認する
- トラブル時の対応について確認する
- 情報の取り扱いについての確認
- 時間厳守・対応姿勢も確認
- 口コミなどの評価や評判もチェック
契約時に隅々まで内容を確認する
支援サービスの詳細な内容や料金設定、支援サービスの内容による金額加算の有無やキャンセル時の対応・料金、重要事項説明書など細かく確認しましょう。
トラブル時の対応について確認する
事故が発生した時や、事前の説明と違うサービス内容だった時などトラブルに関する対応や窓口が設定されているか、確認しておきましょう。
情報の取り扱いについての確認
サービスを受けるにあたり、事業者と手続きのための書類や契約書をかわします。
各種書類の管理や個人情報の取り扱いについて法令を遵守しているかも確認しましょう。
時間厳守・対応姿勢も確認
安全に・安心してサービスを受けられるよう、訪問時間は守れているか、重要事項はわかりやすく説明してくれるか、利用者に対して丁寧な言葉遣いや対応をしてくれるか、なども確認しましょう。
口コミなどの評価や評判もチェック
利用した人からの口コミは心づよいものです。インターネットなどで評価も見ておきましょう。
近所で利用している方がいれば、感想や評判なども聞いておきましょう。
ビジネスパーソンのみなさまへ(まとめ)
- 居宅療養管理指導は、自宅で親・家族を介護することになった時や離れて暮らす親が要介護状態になった時に活用できるサービスです。
- 自宅療養をする中で、服薬指導や栄養管理指導、歯・口腔内のケアなど健康管理についてアドバイスがほしい方におすすめです。
- 自宅への訪問によるサービスのため、通院が難しい方におすすめです。通院にかかる時間や身体的負担の軽減ができます。
- 自宅へ訪問してくれるため、日常の生活空間・スタイルにあわせた最適なアドバイスを得ることができます。
- 居宅療養管理指導は、自宅で落ち着いて療養できる環境を整えたい方におすすめのサービスです。