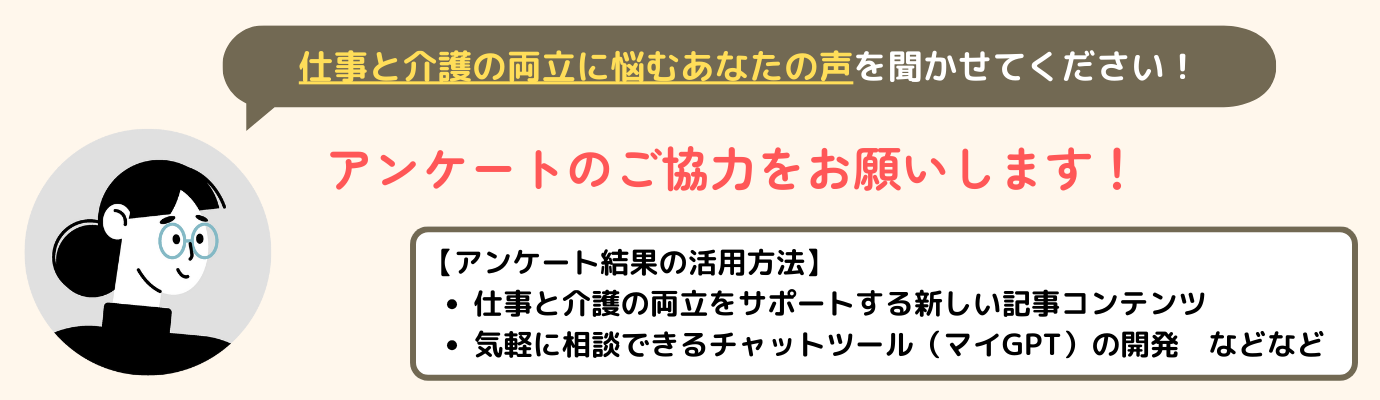介護医療院は、2018年の介護保険法の改定により介護療養型医療施設(療養病床)に代わって新たに認可された介護施設です。
そのためビジネスパーソンのみなさまに、サービス内容や利用方法などがあまり理解がされていないようです。
そこで介護医療院とはどのようなサービスなのか、そしてメリット、デメリットをわかりやすくまとめました。
親や親族の方の最適な介護サービス選びのためにも、正しい知識でより良い施設選びを目指しましょう。
目次
介護医療院とは?
介護医療院は、要介護高齢者が長期的に医療や介護のサポートを受けながら生活する介護保険施設です。2018年に介護療養型医療施設に代わって新たに介護医療院が創設されました。
介護医療院と介護療養型医療施設の主な違いとは、医療ケアを行っていた介護療養型医療施設の役割に加えて、日常生活を送るための支援(生活支援)にも力を入れた点です。
居住スペースは旧来の介護療養型医療施設(療養病床)よりも広く、プライバシーに配慮された部屋が提供されています。
例えば、4人部屋でもベッドの間はパーティションや家具で仕切られており、快適な生活をサポートしています。
介護医療院は、日常的な医学管理と看取り・ターミナルケアを提供する一方で、住まいとしての機能も充実している点が特徴です。
面積や備える機器などについても明確に施設基準が設けられておりますので、ビジネスパーソンのみなさまにとっても、大切なご家族を安心して任せられるのではないでしょうか。
介護保険法での定義
介護保険法において、介護医療院は次のように定義されています。
すこしややこしい内容になるかもしれませんが、この機会に一読してみてください。
介護医療院とは、要介護者であって長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
この定義に基づき、介護医療院の開設者は設備や運営に関して以下のような基準を守らなければなりません。
【介護医療院の設備・運営基準】
- 療養室、診察室、処置室及び機能訓練室、都道府県の条例で定める施設を有すること。
- 厚生労働省令で定める数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有すること。
加えて人員基準に基づいて2種類に分類されています。
【介護医療院の分類2種】
- Ⅰ型介護医療院…介護療養病床相当(主な利用者像は介護療養病床療養機能強化型AB相当)
- Ⅱ型介護医療院…老人保健施設相当以上(主な利用者像はⅠ型より比較的容体が安定した者)
人員に関する基本的な基準
| Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
|---|---|---|
| 医師 | 48対1(施設で3以上) | 100対1(施設で1以上) |
| リハビリ専門職 | 適切な人数 | 適切な人数 |
| 薬剤師 | 150対1 | 300対1 |
| 看護職員 | 6対1 | 6対1 |
| 介護職員 | 5対1 | 6対1 |
| 栄養士または管理栄養士 | 定員100以上で1人 | 定員100以上で1人 |
| 診療放射線技師 | 適切な人数 | 適切な人数 |
| 調理員、事務員等 | 適切な人数 | 適切な人数 |
1つの介護医療院でⅠ型とⅡ型を組み合わせた運営ができる仕組みになっており、より柔軟な人員配置の実現と質の高いサービス提供が担保されていると言えます。
介護医療院のサービス内容
介護医療院で受けられるサービスは大きく分けて3種類です。
| 介護医療院のサービス内容 | |
|---|---|
| ①医療ケア |
|
| ②介護サービス |
|
| ③生活支援 |
|
介護医療院の特徴は、ご家族や地域との交流を持てる生活の場所でありながらも医師や看護師などによる専門的なケアが受けられるのが大きなメリットと言えます。
介護医療院の入居条件
介護医療院に入居できるのは、65歳以上で要介護1~5に認定された方になります。
また、特定疾病を抱えていて要介護認定を受けた40~64歳の方も入所が可能です。特定疾病には、以下のようなものが含まれます。
【国が指定する特定疾病】
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・滞納皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
(※参考サイト:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」)
入所にはこのような条件がございますので、まずはソーシャルワーカーやケアマネジャーなどの専門家に相談すると良いでしょう。
介護医療院にかかる費用
介護医療院への入所にかかる費用は、入所される患者さまの健康状態や、施設のサービス内容によって異なります。下記に一般的にかかる費用を紹介します。
【介護医療院にかかる費用】
- 初期費用(入居一時金)
- 月額費用
- 介護サービス費
初期費用(入居一時金)
介護医療院は公的な介護保険施設のため、Ⅰ型、Ⅱ型共に入居一時金など入居のための初期費用は不要です。
ただし、当然ながら入所時には引っ越し代や日用品を用意する費用が自己負担として発生しますのでご注意ください。
月額費用
月額費用には、介護サービス費(ご利用者負担)、滞在費、食費、日常生活費などが含まれます。
介護医療院は、専門的な医療サービスを提供しているため、他の施設よりもやや費用が高めになります。月額利用料の相場はおおむね8.6~15.5万円程度と言われています。
介護サービス費は、施設の形態(Ⅰ型、Ⅱ型)や部屋のタイプによって異なったり、または家賃や食費などには、所得に応じて負担軽減の仕組みも用意されていますので、事前に施設に問い合わせて確認をしておくと良いでしょう。
介護サービス費
介護サービス費は、施設の形態(Ⅰ型、Ⅱ型)、部屋のタイプによって異なります。
同じ公的施設である特別養護老人ホームと比べると、医師や看護師など人件費の高い職員が多いため少しだけ割高のようです。
【介護医療院の1日あたりのサービス費(利用者負担1割)(円/1日)】
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 714 | 825 | 842 |
| 要介護2 | 824 | 934 | 951 |
| 要介護3 | 1,060 | 1,171 | 1,188 |
| 要介護4 | 1,161 | 1,271 | 1,288 |
| 要介護5 | 1,251 | 1,362 | 1,379 |
介護医療院のメリットは?
介護医療院のメリットをまとめました。特徴を理解することで家族に適した施設選びが出来るようになります。
【介護医療院のメリット】
- 介護ケアと医療ケアの両方が受けられる
- 病院に併設されている施設が多い
- 看取りまでの長期入居ができる
- 生活の場としての環境が整備されている
- リハビリができる
メリット①介護ケアと医療ケアの両方が受けられる
介護医療院には医師や看護師をはじめとしたさまざまな医療スタッフが配置されています。
そのため重度の利用者でも適切な医療とリハビリ、介護施設のような細やかな介護ケアを受けられるのです。
メリット②病院に併設されている施設が多い
介護医療院は病院に併設して作られていることが多いため、万が一容態が悪化してもすぐに関連病院に受け入れてもらえます。
重度の利用者にも安心できる環境と言えるでしょう。
メリット③看取りまでの長期入居ができる
高齢の利用者は入所中に症状が悪化することも少なくありません。
介護医療院は看取りやターミナルケアにも対応していますので、最期まで必要な医療と介護が受けられ安心です。
メリット④生活の場としての環境が整備されている
介護医療院は入院施設ではなく生活施設として創設されました。
談話室やレクリエーションルームが完備されており、家族や地域との交流を持つことで社会との繋がりを感じられます。
メリット⑤リハビリができる
介護医療院には医師や看護師だけでなく、理学療法士や作業療法士などのリハビリテーションスタッフも配置されています。
適切なリハビリを受けることで生活機能の向上が期待できます。
介護医療院のデメリットは?
家族の生活の場でもある介護医療院。利用の前にしっかりとデメリットを理解しておくことも重要です。
【介護医療院のデメリット】
- 利用料が高くなる傾向がある
- 個室がない場合がある
- 施設数がまだ少なく選択肢が少ない
デメリット①利用料が高くなる傾向がある
居住費のかからない医療機関の療養病棟に比べると利用料は高くなります。
入所が長引きトータル費用が高くなる場合もあるため支払い続けられるかどうか事前にしっかりと考えておきましょう。
デメリット②個室がない場合がある
完全個室ではなく、元々多床室だった居室をパーティションなどで仕切って個室化させている施設が少なくありません。
プライバシー確保を重要視される方にはデメリットとなる可能性があります。
デメリット③施設数がまだ少なく選択肢が少ない
厚生労働省によると令和5年12月時点でⅠ型、Ⅱ型あわせた全国の介護医療院の施設数は816とまだ数は多くありません。
お住まいのエリアに施設がない可能性もあります。
介護医療院と他の介護施設サービスとの違い
いざ親やご親族の介護に直面したビジネスパーソンの多くの方は、介護施設もその種類が多いせいか、なかなかそのサービスや入居条件の違いが分からないでいるようです。
入所をする前には、ケアマネジャーや地域包括支援センターの方に相談をされると思われますが、相談する前に予備知識があれば、より具体的な相談が出来るはずです。
介護保健施設4種類を比較しますので、ここで概要を把握していただければと思います。
| 種類 | 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護医療院 | 介護付き有料老人ホーム |
|---|---|---|---|---|
| 入居金 | なし | なし | なし | ・平均値:385.3万円 ・中央値:30万円 (無料の施設もあり) |
| 月額相場 | 10~14.4万円 | 8.8~15.1万円 | 8.6~15.5万円 | 20万円程度 |
| 自立 | × | × | × | ○(介護専用型のみ不可) |
| 要支援1~2 | × | × | × | ○(介護専用型のみ不可) |
| 要介護1~2 | × | ○ | ○ | ○ |
| 要介護3~5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認知症 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 看取り | ○ | ○ | ◎ | ○ |
(○/◎:受け入れ可、×:受け入れ不可)
介護老人保健施設(老健)との違い
介護医療院と介護老人保健施設(老健)は、双方ともに医療ケアが充実している点が類似していますが、入所期間に大きな違いがあります。
| 介護医療院 | 介護老人保健施設 | |
|---|---|---|
| サービス内容 | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス |
| 利用目的 | 長期療養を必要とする人の生活施設 | 在宅復帰を目指した介護とリハビリ(3~6か月) |
| 入居対象者 | 要介護1以上(認知症も対象) | 要介護1以上(認知症も対象) |
| 費用 | 8.6~15.5万円 | 8.8~15.1万円 |
| 要介護度 | 1~5 | 1~5 |
| スタッフ |
|
|
| 施設の雰囲気 |
|
|

介護老人保健施設(いわゆる老健)とは、要介護1以上の高齢者が自宅復帰を目指すための介護保健施設で、おもに「医療ケア」「リハビリテーション」「介護サービス」「認知症ケア」などを行います。 医療ケアでは、医師や看護師が常駐し、健康状態の管理をしてもらえ、かつ病状の変化が有った場合でも迅速に対応出来...
介護老人保健施設(いわゆる老健)とは、要介護1以上の高齢者が自宅復帰を目指すための介護保健施設で、おもに「医療ケア」「リハビリテーション」「介護サービス」「認知症ケア」などを行います。 医療ケアでは、医師や看護師が常駐し、健康状態の管理をしてもらえ、かつ病状の変化が有った場合でも迅速に対応出来...
特別養護老人ホーム(特養)との違い
介護医療院と特別養護老人ホーム(特養)では、医療ケアの有無、入居者の入居条件などに違いがあります。
それ以外の違いについても以下の表で確認してみて下さい。
| 介護医療院 | 特別養護老人ホーム | |
|---|---|---|
| サービス内容 | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス | 生活支援、介護 |
| 利用目的 | 長期療養を必要とする人の生活施設 | 介護を必要とする人の生活施設 |
| 入居対象者 | 要介護1以上(認知症も対象) | 要介護3~5(認知症も対象) |
| 費用 | 8.6~15.5万円 | 10~14.4万円 |
| 要介護度 | 1~5 | 3~5 |
| スタッフ |
|
|
| 施設の雰囲気 |
|
|

特別養護老人ホーム(いわゆる特養)は、要介護3~5の要介護者が入居でき、一般的には民間の介護施設よりも入居費用を抑えられるのが特徴です。 この記事では特別養護老人ホームがどんな介護施設なのか、サービス内容や入居費用、そして入居までの流れなどを細かくご紹介します。 高齢化を背景とした法令を...
特別養護老人ホーム(いわゆる特養)は、要介護3~5の要介護者が入居でき、一般的には民間の介護施設よりも入居費用を抑えられるのが特徴です。 この記事では特別養護老人ホームがどんな介護施設なのか、サービス内容や入居費用、そして入居までの流れなどを細かくご紹介します。 高齢化を背景とした法令を...
介護付き有料老人ホームとの違い
介護医療院と介護付き有料老人ホームの違いとしては、サービス内容や利用目的などがあげられます。
ここではその違いの概要を理解しておくと良いでしょう。
| 介護医療院 | 介護付き有料老人ホーム | |
|---|---|---|
| サービス内容 | 日常生活支援、医療ケア、介護サービス | 生活支援、身体介護、リハビリ、レクリエーション、食事サービス |
| 利用目的 | 長期療養を必要とする人の生活施設 | できる限り自立して毎日を過ごすために日常生活上の支援や機能訓練を行う施設 |
| 入居対象者 | 要介護1以上(認知症も対象) |
|
| 費用 | 8.6~15.5万円 | 20万円程度 |
| 要介護度 | 1~5 | 自立~要介護5 |
| スタッフ |
|
|
| 施設の雰囲気 |
|
|

介護付き有料老人ホームは定額で介護サービスが受けられます。レクリエーションやサークル活動など施設ごとの特色あふれるサービスも魅力です。充実した介護サービスと自分らしい生活が両方得られるサービスとして多くの方に選ばれています。 この記事では、介護付き有料老人ホームとはどんな介護サービスを提供して...
介護付き有料老人ホームは定額で介護サービスが受けられます。レクリエーションやサークル活動など施設ごとの特色あふれるサービスも魅力です。充実した介護サービスと自分らしい生活が両方得られるサービスとして多くの方に選ばれています。 この記事では、介護付き有料老人ホームとはどんな介護サービスを提供して...
介護医療院を選ぶときのポイント
介護医療院は、日常的な医療処置や看取りを提供する施設であり、要介護者にとって重要な選択肢です。
ご家族やビジネスパーソンのみなさまのニーズに合った施設を選ぶことで、安心して生活できる環境を見つけてください。
ポイント①相部屋でも問題なく生活できるか
介護医療院は相部屋の場合が多いです。自分のプライバシーを重視する方は、個室の提供がある施設を選ぶことを検討してください。
ポイント②施設の雰囲気が自分に合うか
訪問して施設の雰囲気を感じることが大切です。スタッフの対応や利用者同士の交流など、自分が快適に過ごせる環境かどうかを確認しましょう。
ポイント③医師や看護職員の対応は丁寧か
医療的なケアを受けるためには、医師や看護職員の対応が重要です。そのためにも施設のスタッフが丁寧で信頼できるかを確認してみてください。
介護医療院への入所から退去までの流れ
「介護医療院を利用するためにどのような手続きを行えば良いのかわからない」という方のために、わかりやすくまとめました。
【STEP.1】要介護認定の申請
市区町村の地域包括支援センターに相談、または市区町村の役場の高齢者福祉窓口に申請。
- 本人が申請できないときは家族が代理で申請可能。
- 家族や親族の支援が受けられない場合、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、入所中の介護保険施設が代行。
【STEP.2】介護認定調査
- 市区町村の職員や委託されたケアマネジャーなどが自宅を訪問し、聞き取り調査。
- かかりつけ医が主治医意見書を作成。かかりつけ医がいない場合は地域包括支援センターのスタッフとかかりつけ医を決めてから診断。
- 結果通知(通常30日程度)。
【STEP.3】利用できる介護医療院を選ぶ
- 厚生労働省の介護サービス情報公表システムで検索する。
- 病院のソーシャルワーカーやケアマネジャーに相談(入院している場合)。
- 市区町村役場に相談。
【STEP.3】資料請求や施設見学を行う
- ショートステイが可能であれば行う。
- 施設の雰囲気や生活状況、サービス、設備のクオリティなどをチェック。
【STEP.4】申し込み
- 入居申込書や必要書類を提出。診療情報提供書や健康診断書などの書類の準備や審査に時間がかかるため、余裕をもって準備しましょう。
- 申し込み後に施設スタッフとの面談を実施。
【STEP.5】契約・利用開始
- 面談を実施して療養方針などを詳細に決めます。
- 施設の空き状況などに応じて入居日が決定します。
【STEP.6】退所
(自宅退院、他施設への転所、介護医療院での永眠などの理由)
ビジネスパーソンのみなさまへ(まとめ)
この記事では介護医療院のサービス内容や他介護施設との違い、メリット・デメリットを紹介してきました。
改めて、介護医療院についてまとめます。
- 介護医療院は要介護高齢者が最期まで人としての尊厳を守りながら長期療養できる生活施設です。
- 2018年に創設されたばかりでまだ全国的に施設数が少ないものの、ニーズが高いことから今後ますます数が増えることが期待できます。
- 後悔のない施設選びを行うには利用者の病状や症状、意向などをよく知る主治医やケアマネジャー、ソーシャルワーカーなどの専門家にしっかりと相談し、さまざまな施設を比較検討することが大切です。
- 質の高い医療ケアと介護ケアの両方が受けられるのが最大のメリットです。急な容体の変化にも対応できるため、医療区分や健康上の問題により他の施設で入居を断られた方にもおすすめできる介護施設であると言えます。